03
「善逸、起きたのか?」
好きな男が自宅のキッチンでお嫁さんのまねごとをしている。
目が覚めたら文字通りそんな光景が飛び込んできたものだから、とうとう今世での徳を使い切ってその代償として召されてしまうのかと俺は覚悟を決める。だってそうでもないと採算が合わない。突然熱を出して寝込んだという状況も召されるのにいい理由だろう。誰にってそりゃあ、神様や仏様やその類いの存在にとってである。
「梅と鮭、好きな方を乗せてやれるぞ。どっちがいい」
「鮭」
「わかった!」
じきに換気扇の音が止まってエプロン姿のお嫁さん──好きな男──幼馴染──もとい炭治郎が振り返る。たった今こしらえたばかりのおかゆが入った土鍋を手に。できたぞと女神のように微笑む彼に思わず息をのむ。これが己の冥土の土産なのだ。じゃあ俺健闘した方なんじゃないの? だってだって、結構、幸せな方じゃない?
「悪い、熱を出してたんだったな……。具合はどうだ? ちょっとは下がったか?」
そばにあったローテーブルに鍋敷きを敷いて下ろすとベッドのそばにしゃがんだ炭治郎は俺の額に手を伸ばす。
「汗をあまりかいてないみたいだな。熱を上げきった方がすぐよくなると聞くが……俺は経験値がなくて……あれっ善逸!? 顔が真っ赤だぞ!! 急に熱が上がったのか!? 大丈夫か!?」
「いい、いいって大丈夫大丈夫! 病人の隣で叫ぶんじゃないよ!」
「ああ、すまない善逸……いやそんな、だからって寝床まで変えなくても、静かにするからおとなしく寝てたほうが」
「トイレに! 行ってきます!!」
「そ、そうか、付き添うか……?」
「いい! お気遣いありがとうねえ!?」
一気に上がった心拍がめまいも頭痛も束の間遠ざけた。それでもこれがただの現実であるなら、そっちの方が今の俺には耐えがたい。意味もなく便器に座って立ち上がるまで、祈るように執念深く頬を何度も何度もつねり続ける。
***
小学中学高校大学。付き合いの年数を数えようとしたら両の指をゆうに越える同性の友人を好いているとふいに気付いたのは昨日のことだ。
さすがに受けとめきれず熱が出た。炭治郎に服を見に行くのに付き合ってくれと頼んだ約束の日の朝のことだった。謝罪とともにメッセージを送って悪いと思いつつそのまま寝込んだ。膨大な情緒処理を片付けるべく泥のように眠り込んでいた俺を叩き起こしたのは幾度も鳴り続けていたらしいチャイムの音だった。──俺にその処理を強行させている張本人による。
「母さんがひとり暮らしで風邪をひくと大変だからお見舞いしてやりなさいって。眠っているところ悪かった」
「そうか、実家に帰ってたのかお前は……。え、もう年明ける?」
「そうだな。あさってには明ける」
「うわ。正月の準備もあるだろうに悪かったよ。わざわざありがとうね。うつしたらよくないし早く帰んな……ってなになになんか上がろうとしてない? 炭治郎? 玄関先でいいよ?」
「いや、作るぞ」
「え? なに? 飯? いいよ、レンチンぐらいできるって」
「いや、……作る」
「ちょっと待って。なんか袋でかいな。何持ってきたの。って、えっ。何これ。俺の家で正月の準備しようとしてる?」
「だから、つ、作るって!」
おいおいお見舞いと看病は意味が違うぞと説きながら、だからってたらふく買い込まれた生鮭の切り身やら米やら味噌やら野菜やらを冷蔵庫にしまう気力は残っていない。勘違いに気を落としているらしい炭治郎もおかしいやら気の毒やらで、結果家に上げてキッチンに通してしまった。
「大晦日とか正月とかは良いのかよ、俺んちはあんまそういうのないからわかんないけどさあ……」
「元々そうだったが、俺が実家を出てからはみんなしっかりしてる。ひとり抜けたってもう平気だよ」
「そっかあ……」
「なんならこのまま年を越してもいいな」
ワンルームに響く明朗な笑い声に、一昨日までなら何も考えず同調していたしなんならそう誘っていただろう。再度潜りこんだベッドの中から炭治郎に声を届けるには誤魔化しのきかない発音をしないといけない。そんな風に無理に笑うと今は震えてしまいそうだ。珍しく落ちた沈黙に炭治郎が振り返るのが見える。邪な念で視界が埋まって、せめて肩まで毛布をかぶる。
「すまない。はしゃぎすぎたな。善逸は寝ててくれ。作り終わったときに寝てたら俺はそのまま帰るから、気にしなくていい」
「悪いな。甘える」
「ああ」
どうしても好きだな。そしてずっと好きだろう。でも告白は無理だろうな。一生無理だろう。相反する感情が頭痛を引き起こしているみたいで、何もかも手放して眠り込むには難しい状況だったけれど、だからこっそりちょっと泣いたけど、万全じゃない体調も幸いしてなんとか入眠には成功していた。らしい。
***
「昨日から何も食ってなかったんだよ」
「それは腹が減ってるだろう。多めに作ったから明日までもつぞ」
「あんがとね。助かるわ。こういうとき、コンビニのゼリー吸うぐらいしか選択肢なかったからさ」
「そうか……ああ、降りなくて良いぞ。俺が冷ましてやるから」
「炭治郎の看病スキルって完全に家族向けなんよ。ひとりで食えるっつーの」
「無理をするな。ほら。あーん」
「え? ちょ……」
れんげを差し出される段になって押し返すのも無粋か? 俺の頭が回ってないだけか? 検討する暇もなく唇を撫でる湯気と出汁の匂いにつられてひな鳥のように口を開けている。
「う、ま~……ッ。美味いよ炭治郎。最高」
「ほら、鮭も」
「ん……あつ、あ~うま……」
「いっぱい食べてはやく治ると良いな」
大学も休みに入って暴飲暴食が続いていたせいだろう。質素な温もりと味付けがやたらと体中に染みわたる。部屋が冷えていたらしいというのはあったまってから気付くものでもある。夢中になって出されるままに食べているうちにあっという間に鍋の中身はなくなっていった。
「そんなに食べてもらえたら作りがいがあるよ」
「ん、だってこれマジでうまい、毎日でも食いた」
い、と最後の音を吐き出した俺と、炭治郎の目が合う。音が鳴りそうなくらい、それはそれはもう。
実際それは俺の思い込み以上にはならない。そのまま好きだと口走れたら、もしくは口づけてしまえたら。しかし、衝動的だろうがなんだろうがそんな愛情表現はすべてが壊れてしまうスイッチにそのまま成り代わる。
「そんなに言ってくれるのは善逸くらいだろうな」
「……そんなわけあるかよ。歴代の彼女も軒並み絶賛だったろ、俺知ってるんだからな」
手を、出してしまいそうだ。それどころか良いんじゃないかと唆そうとすらする本能のためにそんな話題を振った。
炭治郎は頬をかきながら「まあ不味いと言われたことはなかったな」と、きっと誰かを思い出しながらつぶやいている。どうか思い出してくれよ。一時の判断で突っ走らないでくれよ。互いのAVの趣味まで知り尽くしてるくらいには仲が良く、だからこれからできる彼女の愚痴も惚気話もこれから何回だって交わすだろう。結婚式にだって招待し合って友人代表のスピーチだってお互いに贈って、いずれは子ども同士もこんな仲になるんだろう。そんな未来が手に入るんだろう。
一生いちばん仲の良い友人同士。それはきっと変に恋人同士として縁をつなぐよりもよっぽど強固だ。
目をつむる時間は、きっと一瞬で済む。これから果てしなく続く人生に比べたら、正真正銘たった一瞬なんだろう。
でも。
「やっぱりさあ」
「ん?」
「今更だけど、移したら悪いし。俺ももうちょい寝たいし、今日は帰ってくんない?」
「……」
言い方に気を遣う余裕はなかった。ここまでしてくれたのにと思い至ったのも、やっぱり今更だった。炭治郎の悲しそうにゆがんだ眉と、それを隠そうとするいびつな微笑みに、気付く。
「すまない。迷惑だったな。連絡すら入れなかったし。返すのも負担かと思って勝手に押しかけてしまった」
「えっちょっと待って泣いて、……え、炭治郎、え、なんで、どしたの」
「泣いてない、何を言ってるんだ? こんなことで泣くわけないだろう。善逸の、目が、おかしい、んじゃ……」
「待って待ってボロ泣きじゃんねえ!? わかってるよねえ自分でも!? いいよここにいなよ年越しまでなんて言わず正月丸々居てくれよ、追い出したかったわけじゃないんだよむしろ嬉しくて嬉しすぎて俺は」
「いいんだ!! とにかく帰る!!! ッ……離せ!」
「お前おい! 今っ! 俺に頭突きしようとしたろ!! 病人だぞ信じらんねえこれ以上体力使わせんなよ大人しくここにいろっつってんでしょうがあぁああ!?」
しかし──さすがに不発だったとはいえ──頭突きまで繰り出す炭治郎を止められたためしは、俺にはもちろんない。ましてや体力面で圧倒的に今は不利だ。振り返りすらせずまっすぐ部屋をあとにする炭治郎に結局追いつけなかった。
静まりかえった部屋と空っぽの土鍋を前にどんなメッセージを送ればいいかなんて思いつくはずもなくて、これからずっとこんな調子で変なきっかけで喧嘩とかしたりすんのかなあって考えたら気が滅入るばっかりで。もしかしたら実際顔を合わせたらこれが恋なんて気の迷いだったって鼻で笑えるかもっていう期待も完全に潰れていて、炭治郎が泣いてたのもわけわかんなくて、それで、それから、俺は──
眠りに落ちていたらしい。完全なふて寝だ。
そんな寝起きの耳に、こんこんこんと控えめなノックの音が響く。
空耳じゃないという妙な確信があった。置き配には心当たりがない。飛び起きて俊足で玄関へ向かう。ドアを開けたらレジ袋がノブに引っかかって揺れていて、でも、肝心の炭治郎がいない。
『さっきは悪かった。鍵はポストに入れてある。レンチンで作れるものを入れておいたから食べてくれ。治ったら連絡が欲しい。よいお年を。』
「またたらふく詰め込んでよ……俺、男三人ぐらいで暮らしてると思われてる?」
俺とお前でちょうどなんじゃないの。って、ちょっと待ってくれたら言えたのに。そんで仲直りできたのに。こういうときばっか俺より足早いよな。
悪かったよ。好きなんて気付いちゃって想っちゃって取り乱して悪かったよ。もう言わないよ。友だちとしてやってこうよ。じゃないともたないよ。炭治郎がいなくなる方が俺はもたない。
今日で何度目の涙だろうか。ぼやけて滲んだ視界に夕陽が暖かくて、でも年の瀬の空気は凍てついていて、結局長居できずひとりの部屋に踵を返す。思い出せるおかゆの味があるだけ幸福だと、思い込めばきっと本当にそうなる世界が引き続き広がっている。
ないない
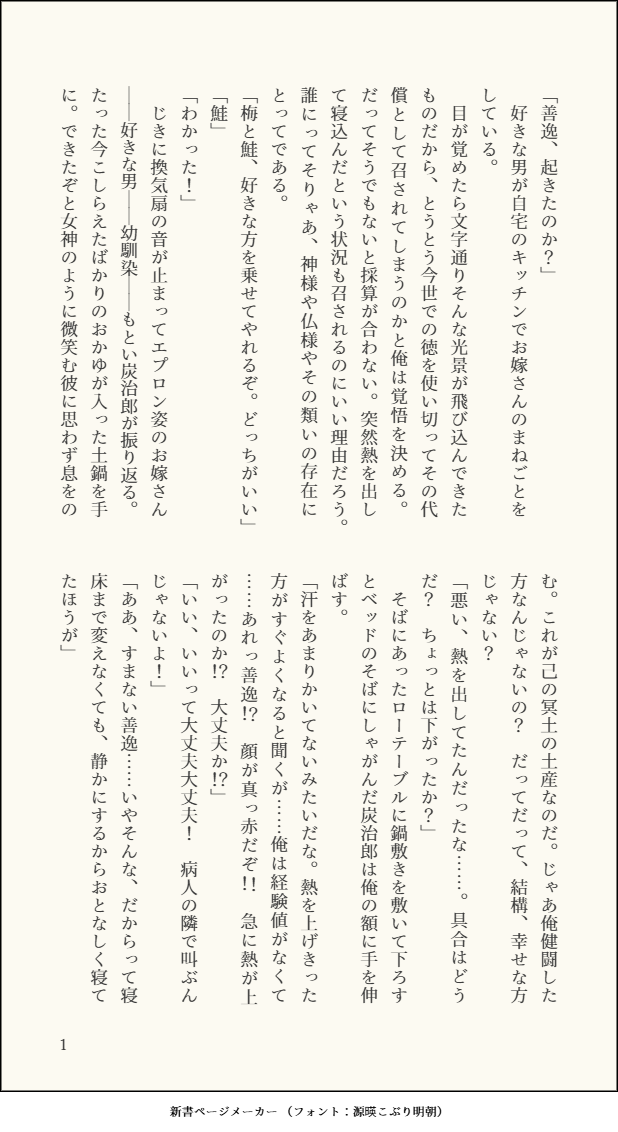
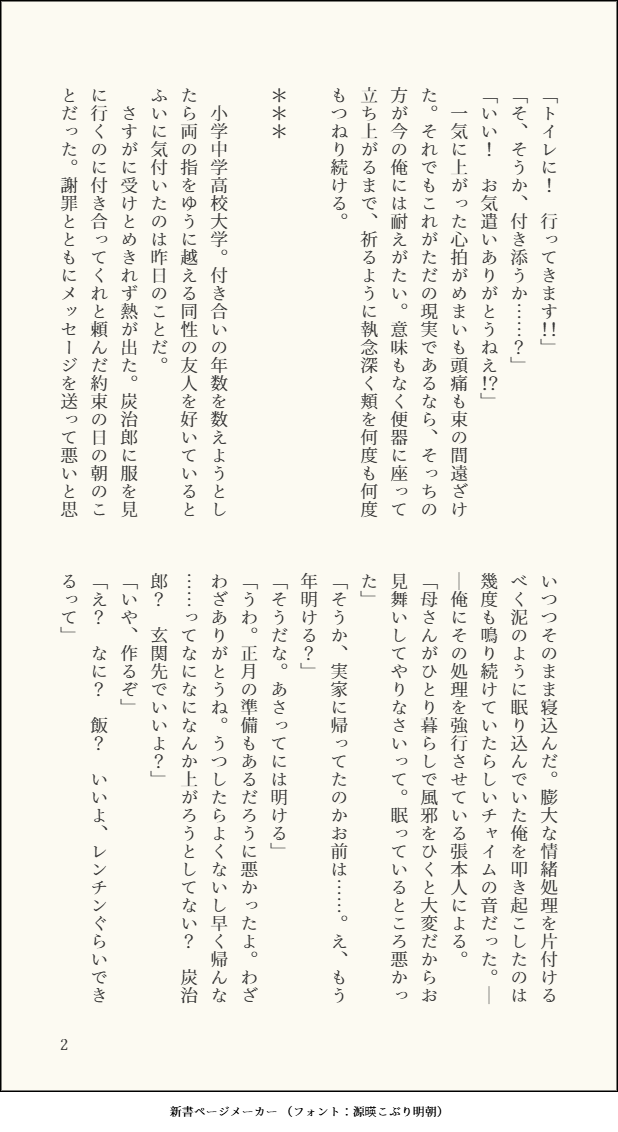
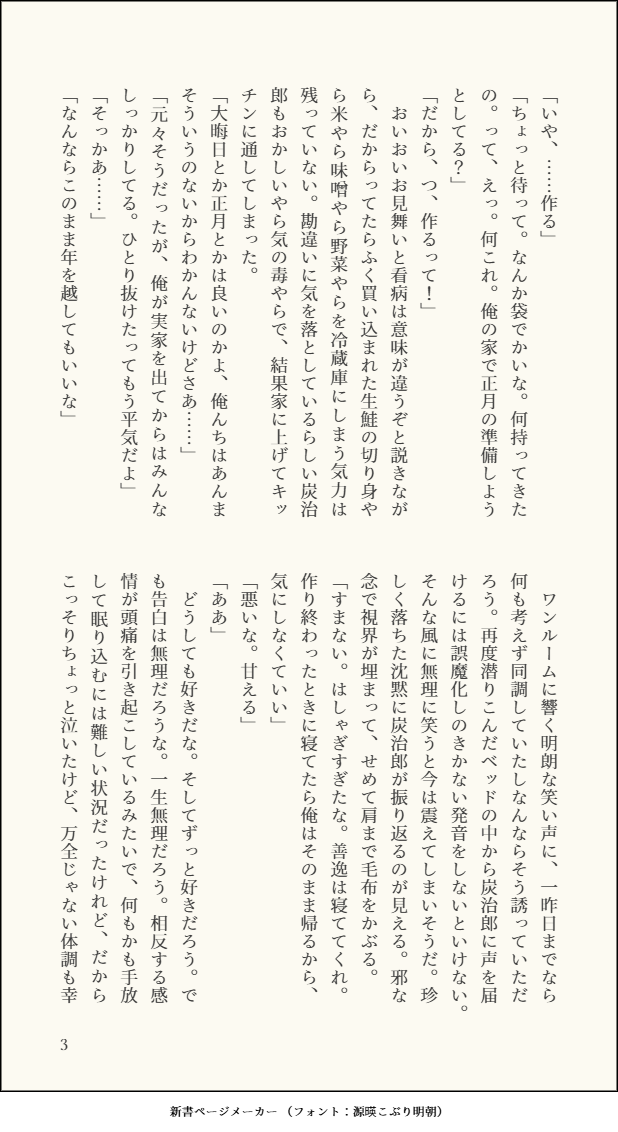
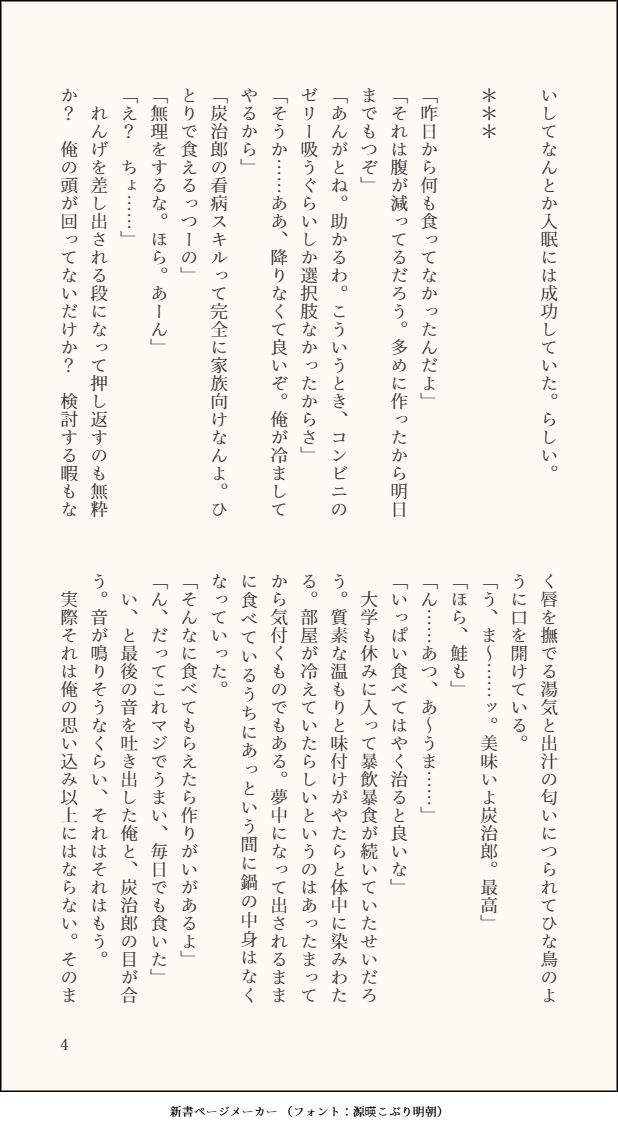
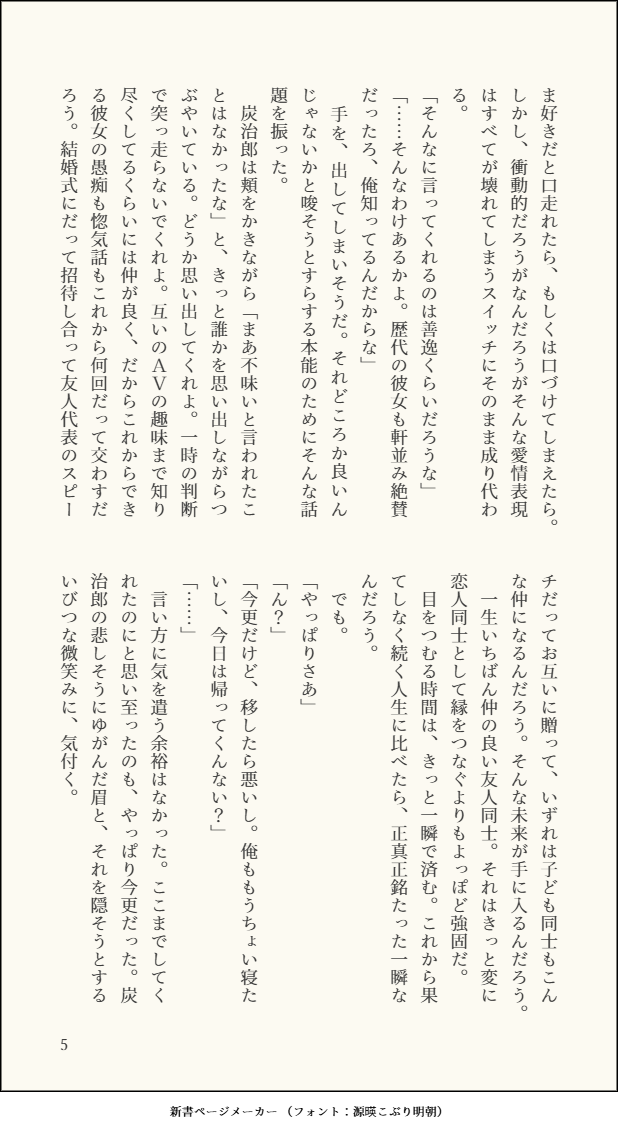
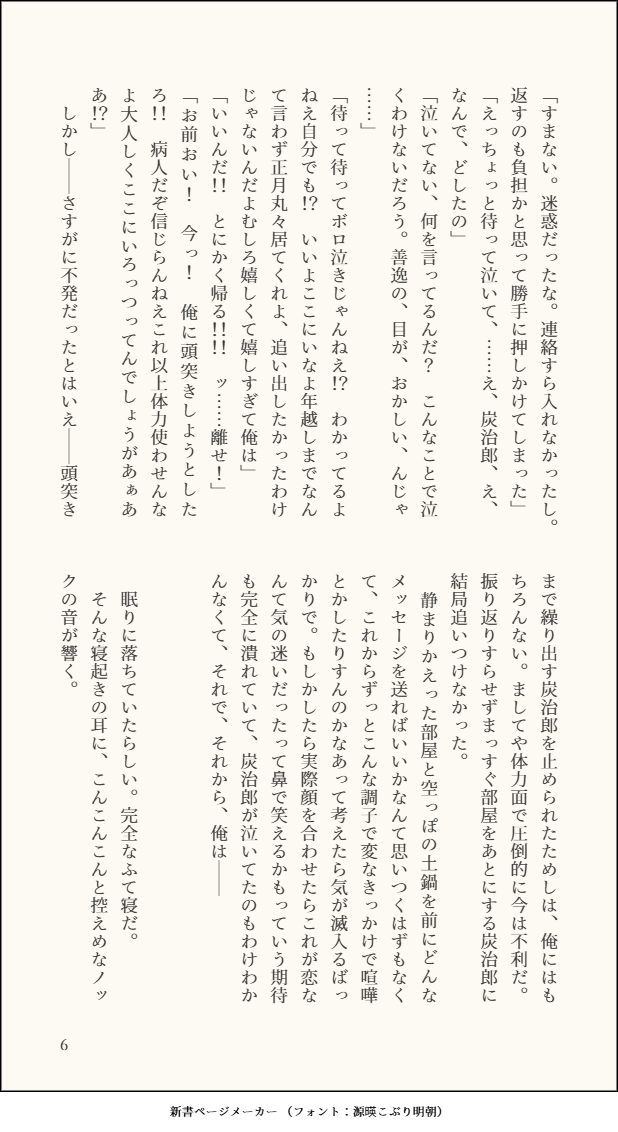
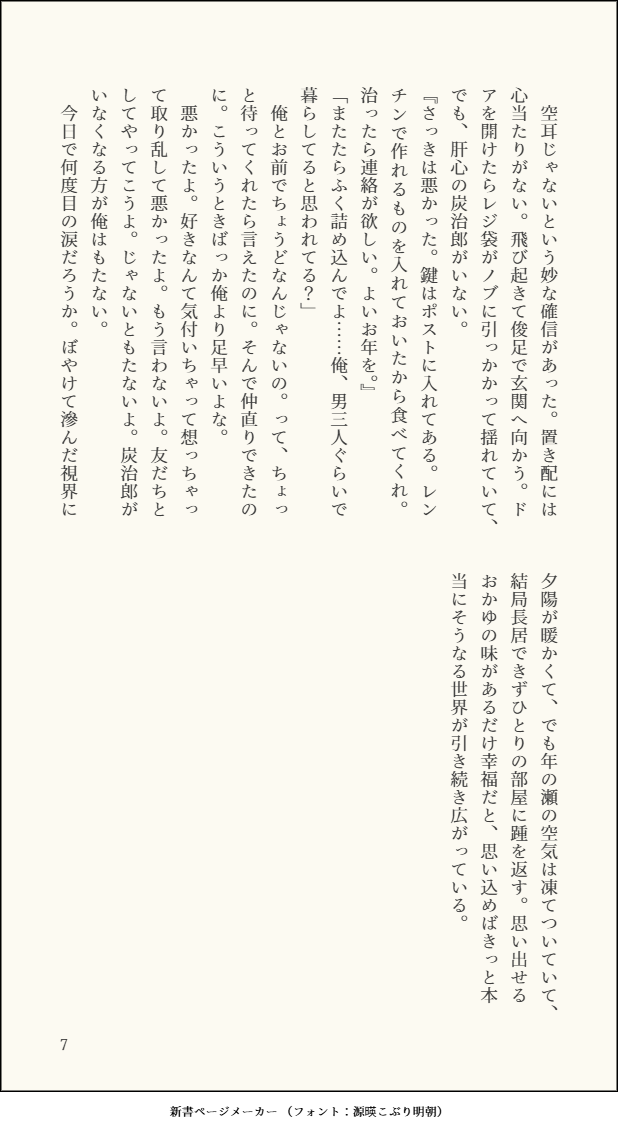
ないない
「善逸、起きたのか?」
好きな男が自宅のキッチンでお嫁さんのまねごとをしている。
目が覚めたら文字通りそんな光景が飛び込んできたものだから、とうとう今世での徳を使い切ってその代償として召されてしまうのかと俺は覚悟を決める。だってそうでもないと採算が合わない。突然熱を出して寝込んだという状況も召されるのにいい理由だろう。誰にってそりゃあ、神様や仏様やその類いの存在にとってである。
「梅と鮭、好きな方を乗せてやれるぞ。どっちがいい」
「鮭」
「わかった!」
じきに換気扇の音が止まってエプロン姿のお嫁さん──好きな男──幼馴染──もとい炭治郎が振り返る。たった今こしらえたばかりのおかゆが入った土鍋を手に。できたぞと女神のように微笑む彼に思わず息をのむ。これが己の冥土の土産なのだ。じゃあ俺健闘した方なんじゃないの? だってだって、結構、幸せな方じゃない?
「悪い、熱を出してたんだったな……。具合はどうだ? ちょっとは下がったか?」
そばにあったローテーブルに鍋敷きを敷いて下ろすとベッドのそばにしゃがんだ炭治郎は俺の額に手を伸ばす。
「汗をあまりかいてないみたいだな。熱を上げきった方がすぐよくなると聞くが……俺は経験値がなくて……あれっ善逸!? 顔が真っ赤だぞ!! 急に熱が上がったのか!? 大丈夫か!?」
「いい、いいって大丈夫大丈夫! 病人の隣で叫ぶんじゃないよ!」
「ああ、すまない善逸……いやそんな、だからって寝床まで変えなくても、静かにするからおとなしく寝てたほうが」
「トイレに! 行ってきます!!」
「そ、そうか、付き添うか……?」
「いい! お気遣いありがとうねえ!?」
一気に上がった心拍がめまいも頭痛も束の間遠ざけた。それでもこれがただの現実であるなら、そっちの方が今の俺には耐えがたい。意味もなく便器に座って立ち上がるまで、祈るように執念深く頬を何度も何度もつねり続ける。
***
小学中学高校大学。付き合いの年数を数えようとしたら両の指をゆうに越える同性の友人を好いているとふいに気付いたのは昨日のことだ。
さすがに受けとめきれず熱が出た。炭治郎に服を見に行くのに付き合ってくれと頼んだ約束の日の朝のことだった。謝罪とともにメッセージを送って悪いと思いつつそのまま寝込んだ。膨大な情緒処理を片付けるべく泥のように眠り込んでいた俺を叩き起こしたのは幾度も鳴り続けていたらしいチャイムの音だった。──俺にその処理を強行させている張本人による。
「母さんがひとり暮らしで風邪をひくと大変だからお見舞いしてやりなさいって。眠っているところ悪かった」
「そうか、実家に帰ってたのかお前は……。え、もう年明ける?」
「そうだな。あさってには明ける」
「うわ。正月の準備もあるだろうに悪かったよ。わざわざありがとうね。うつしたらよくないし早く帰んな……ってなになになんか上がろうとしてない? 炭治郎? 玄関先でいいよ?」
「いや、作るぞ」
「え? なに? 飯? いいよ、レンチンぐらいできるって」
「いや、……作る」
「ちょっと待って。なんか袋でかいな。何持ってきたの。って、えっ。何これ。俺の家で正月の準備しようとしてる?」
「だから、つ、作るって!」
おいおいお見舞いと看病は意味が違うぞと説きながら、だからってたらふく買い込まれた生鮭の切り身やら米やら味噌やら野菜やらを冷蔵庫にしまう気力は残っていない。勘違いに気を落としているらしい炭治郎もおかしいやら気の毒やらで、結果家に上げてキッチンに通してしまった。
「大晦日とか正月とかは良いのかよ、俺んちはあんまそういうのないからわかんないけどさあ……」
「元々そうだったが、俺が実家を出てからはみんなしっかりしてる。ひとり抜けたってもう平気だよ」
「そっかあ……」
「なんならこのまま年を越してもいいな」
ワンルームに響く明朗な笑い声に、一昨日までなら何も考えず同調していたしなんならそう誘っていただろう。再度潜りこんだベッドの中から炭治郎に声を届けるには誤魔化しのきかない発音をしないといけない。そんな風に無理に笑うと今は震えてしまいそうだ。珍しく落ちた沈黙に炭治郎が振り返るのが見える。邪な念で視界が埋まって、せめて肩まで毛布をかぶる。
「すまない。はしゃぎすぎたな。善逸は寝ててくれ。作り終わったときに寝てたら俺はそのまま帰るから、気にしなくていい」
「悪いな。甘える」
「ああ」
どうしても好きだな。そしてずっと好きだろう。でも告白は無理だろうな。一生無理だろう。相反する感情が頭痛を引き起こしているみたいで、何もかも手放して眠り込むには難しい状況だったけれど、だからこっそりちょっと泣いたけど、万全じゃない体調も幸いしてなんとか入眠には成功していた。らしい。
***
「昨日から何も食ってなかったんだよ」
「それは腹が減ってるだろう。多めに作ったから明日までもつぞ」
「あんがとね。助かるわ。こういうとき、コンビニのゼリー吸うぐらいしか選択肢なかったからさ」
「そうか……ああ、降りなくて良いぞ。俺が冷ましてやるから」
「炭治郎の看病スキルって完全に家族向けなんよ。ひとりで食えるっつーの」
「無理をするな。ほら。あーん」
「え? ちょ……」
れんげを差し出される段になって押し返すのも無粋か? 俺の頭が回ってないだけか? 検討する暇もなく唇を撫でる湯気と出汁の匂いにつられてひな鳥のように口を開けている。
「う、ま~……ッ。美味いよ炭治郎。最高」
「ほら、鮭も」
「ん……あつ、あ~うま……」
「いっぱい食べてはやく治ると良いな」
大学も休みに入って暴飲暴食が続いていたせいだろう。質素な温もりと味付けがやたらと体中に染みわたる。部屋が冷えていたらしいというのはあったまってから気付くものでもある。夢中になって出されるままに食べているうちにあっという間に鍋の中身はなくなっていった。
「そんなに食べてもらえたら作りがいがあるよ」
「ん、だってこれマジでうまい、毎日でも食いた」
い、と最後の音を吐き出した俺と、炭治郎の目が合う。音が鳴りそうなくらい、それはそれはもう。
実際それは俺の思い込み以上にはならない。そのまま好きだと口走れたら、もしくは口づけてしまえたら。しかし、衝動的だろうがなんだろうがそんな愛情表現はすべてが壊れてしまうスイッチにそのまま成り代わる。
「そんなに言ってくれるのは善逸くらいだろうな」
「……そんなわけあるかよ。歴代の彼女も軒並み絶賛だったろ、俺知ってるんだからな」
手を、出してしまいそうだ。それどころか良いんじゃないかと唆そうとすらする本能のためにそんな話題を振った。
炭治郎は頬をかきながら「まあ不味いと言われたことはなかったな」と、きっと誰かを思い出しながらつぶやいている。どうか思い出してくれよ。一時の判断で突っ走らないでくれよ。互いのAVの趣味まで知り尽くしてるくらいには仲が良く、だからこれからできる彼女の愚痴も惚気話もこれから何回だって交わすだろう。結婚式にだって招待し合って友人代表のスピーチだってお互いに贈って、いずれは子ども同士もこんな仲になるんだろう。そんな未来が手に入るんだろう。
一生いちばん仲の良い友人同士。それはきっと変に恋人同士として縁をつなぐよりもよっぽど強固だ。
目をつむる時間は、きっと一瞬で済む。これから果てしなく続く人生に比べたら、正真正銘たった一瞬なんだろう。
でも。
「やっぱりさあ」
「ん?」
「今更だけど、移したら悪いし。俺ももうちょい寝たいし、今日は帰ってくんない?」
「……」
言い方に気を遣う余裕はなかった。ここまでしてくれたのにと思い至ったのも、やっぱり今更だった。炭治郎の悲しそうにゆがんだ眉と、それを隠そうとするいびつな微笑みに、気付く。
「すまない。迷惑だったな。連絡すら入れなかったし。返すのも負担かと思って勝手に押しかけてしまった」
「えっちょっと待って泣いて、……え、炭治郎、え、なんで、どしたの」
「泣いてない、何を言ってるんだ? こんなことで泣くわけないだろう。善逸の、目が、おかしい、んじゃ……」
「待って待ってボロ泣きじゃんねえ!? わかってるよねえ自分でも!? いいよここにいなよ年越しまでなんて言わず正月丸々居てくれよ、追い出したかったわけじゃないんだよむしろ嬉しくて嬉しすぎて俺は」
「いいんだ!! とにかく帰る!!! ッ……離せ!」
「お前おい! 今っ! 俺に頭突きしようとしたろ!! 病人だぞ信じらんねえこれ以上体力使わせんなよ大人しくここにいろっつってんでしょうがあぁああ!?」
しかし──さすがに不発だったとはいえ──頭突きまで繰り出す炭治郎を止められたためしは、俺にはもちろんない。ましてや体力面で圧倒的に今は不利だ。振り返りすらせずまっすぐ部屋をあとにする炭治郎に結局追いつけなかった。
静まりかえった部屋と空っぽの土鍋を前にどんなメッセージを送ればいいかなんて思いつくはずもなくて、これからずっとこんな調子で変なきっかけで喧嘩とかしたりすんのかなあって考えたら気が滅入るばっかりで。もしかしたら実際顔を合わせたらこれが恋なんて気の迷いだったって鼻で笑えるかもっていう期待も完全に潰れていて、炭治郎が泣いてたのもわけわかんなくて、それで、それから、俺は──
眠りに落ちていたらしい。完全なふて寝だ。
そんな寝起きの耳に、こんこんこんと控えめなノックの音が響く。
空耳じゃないという妙な確信があった。置き配には心当たりがない。飛び起きて俊足で玄関へ向かう。ドアを開けたらレジ袋がノブに引っかかって揺れていて、でも、肝心の炭治郎がいない。
『さっきは悪かった。鍵はポストに入れてある。レンチンで作れるものを入れておいたから食べてくれ。治ったら連絡が欲しい。よいお年を。』
「またたらふく詰め込んでよ……俺、男三人ぐらいで暮らしてると思われてる?」
俺とお前でちょうどなんじゃないの。って、ちょっと待ってくれたら言えたのに。そんで仲直りできたのに。こういうときばっか俺より足早いよな。
悪かったよ。好きなんて気付いちゃって想っちゃって取り乱して悪かったよ。もう言わないよ。友だちとしてやってこうよ。じゃないともたないよ。炭治郎がいなくなる方が俺はもたない。
今日で何度目の涙だろうか。ぼやけて滲んだ視界に夕陽が暖かくて、でも年の瀬の空気は凍てついていて、結局長居できずひとりの部屋に踵を返す。思い出せるおかゆの味があるだけ幸福だと、思い込めばきっと本当にそうなる世界が引き続き広がっている。
ないない
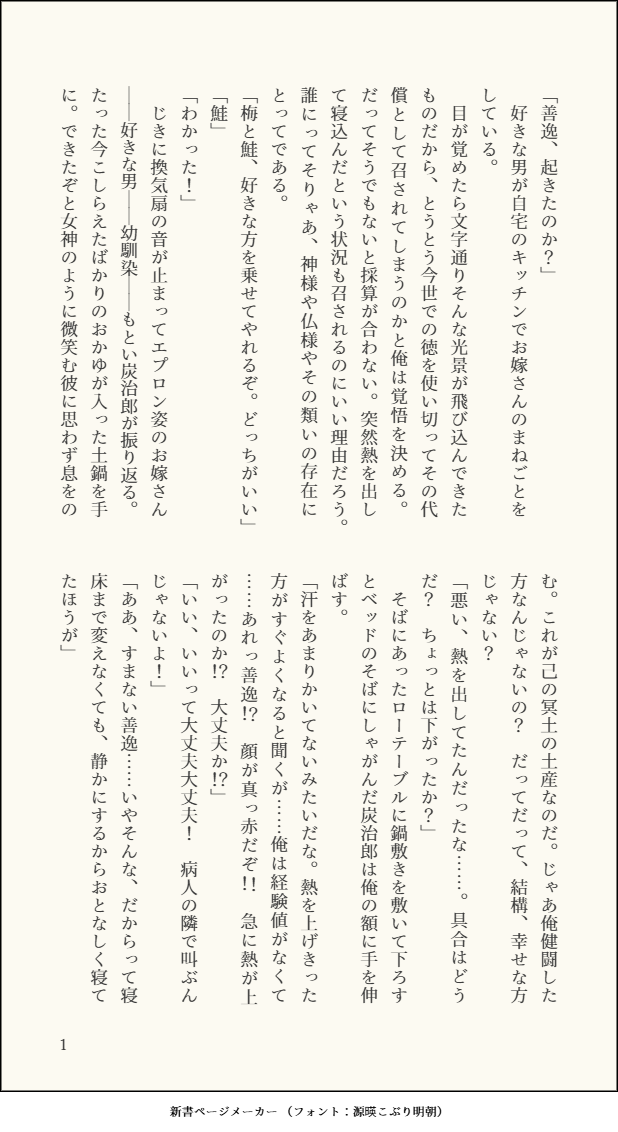
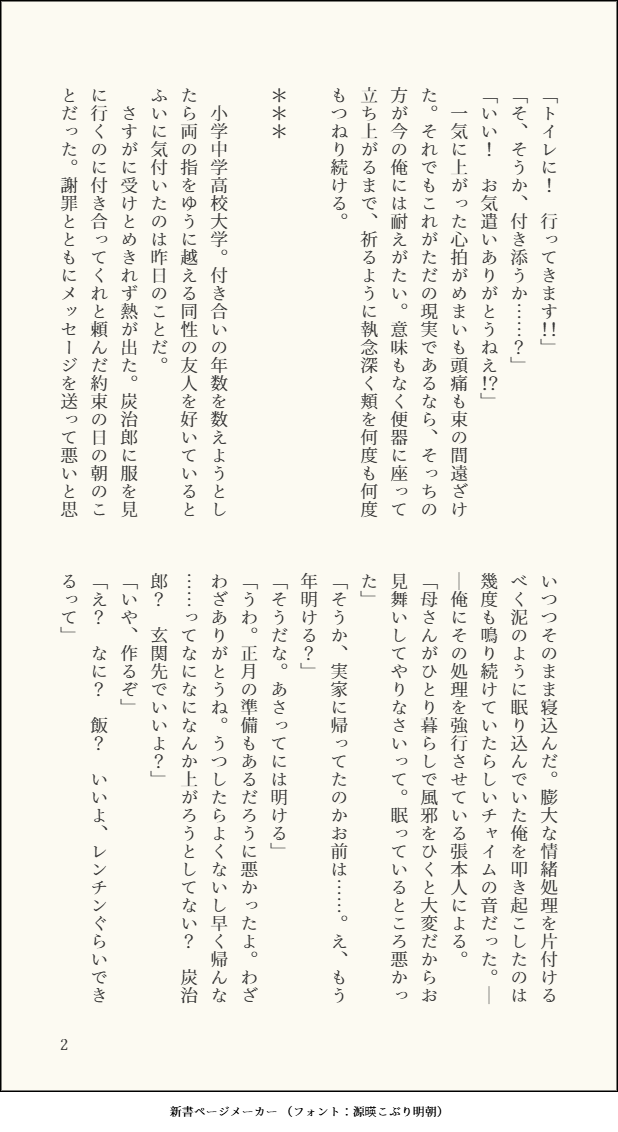
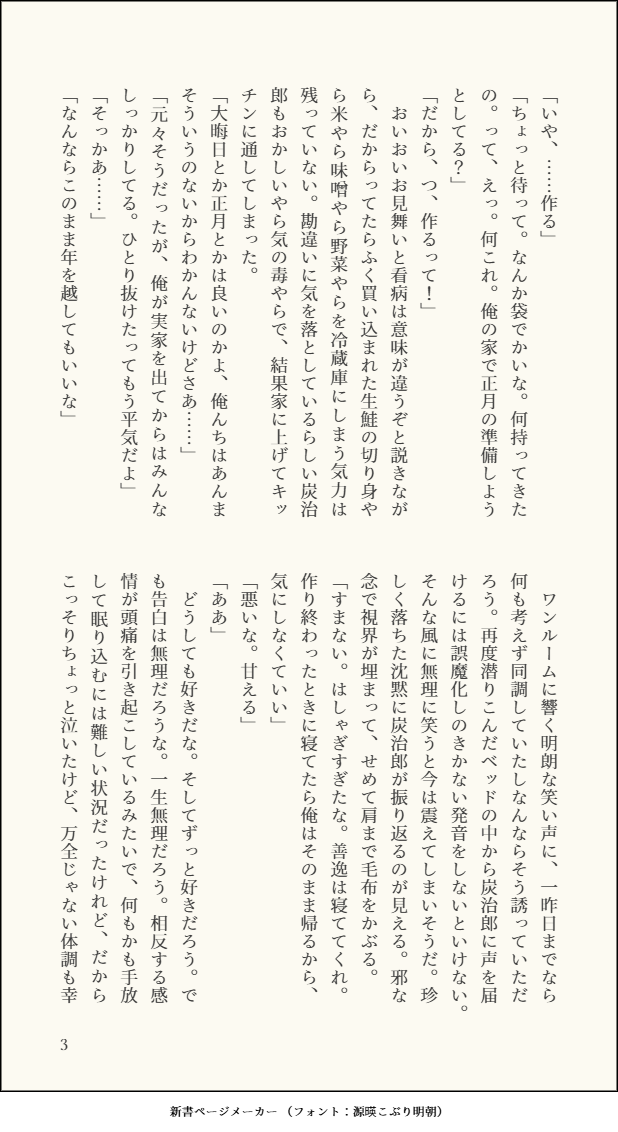
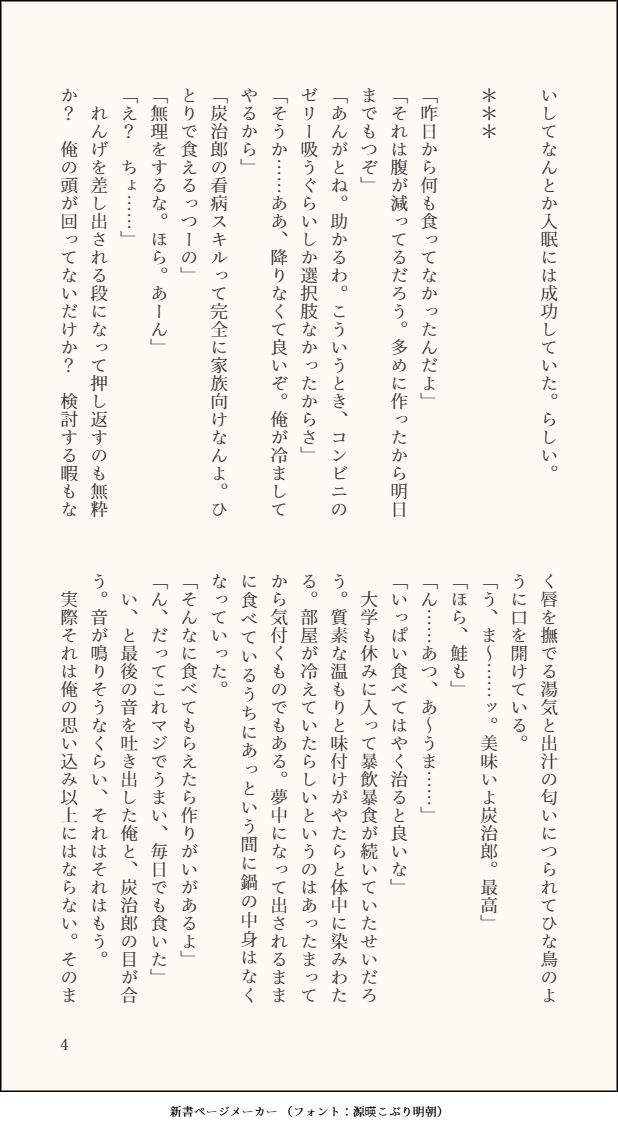
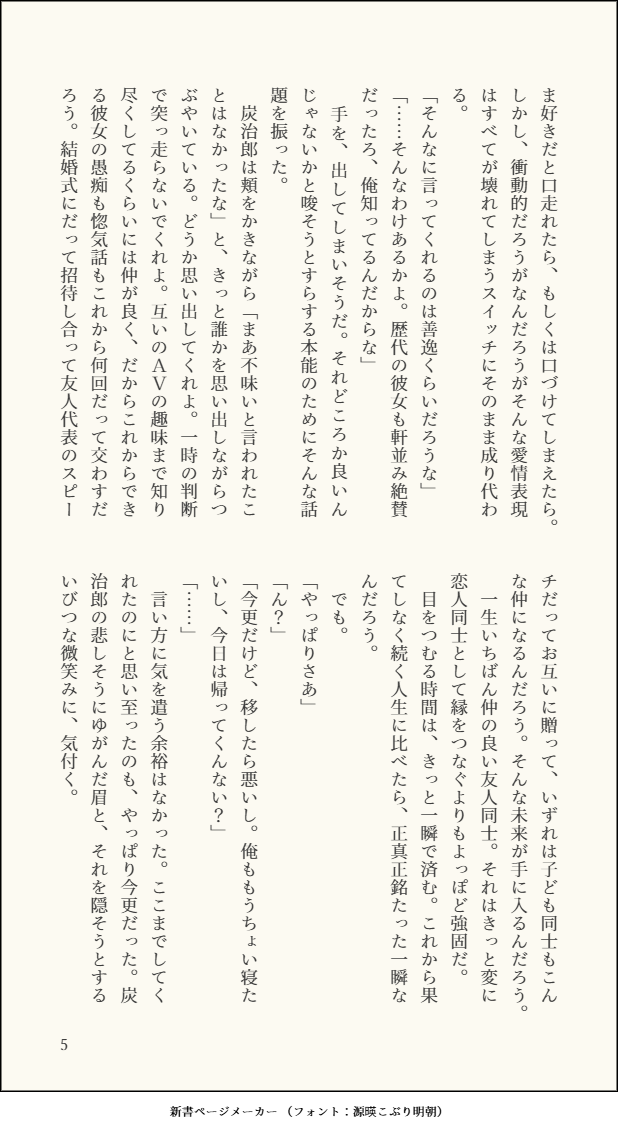
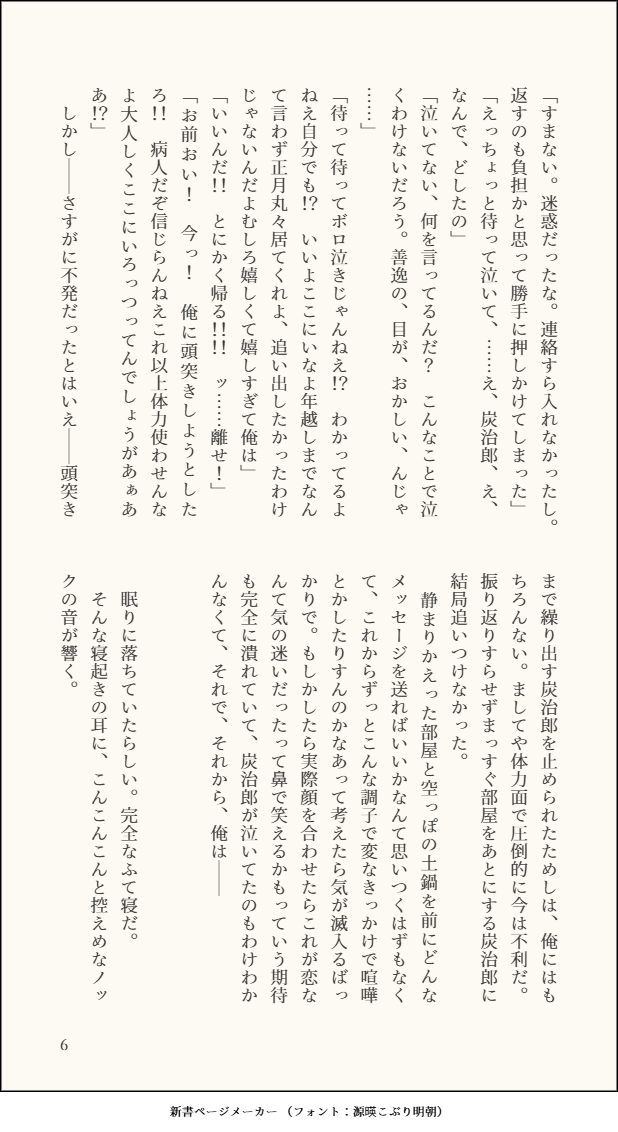
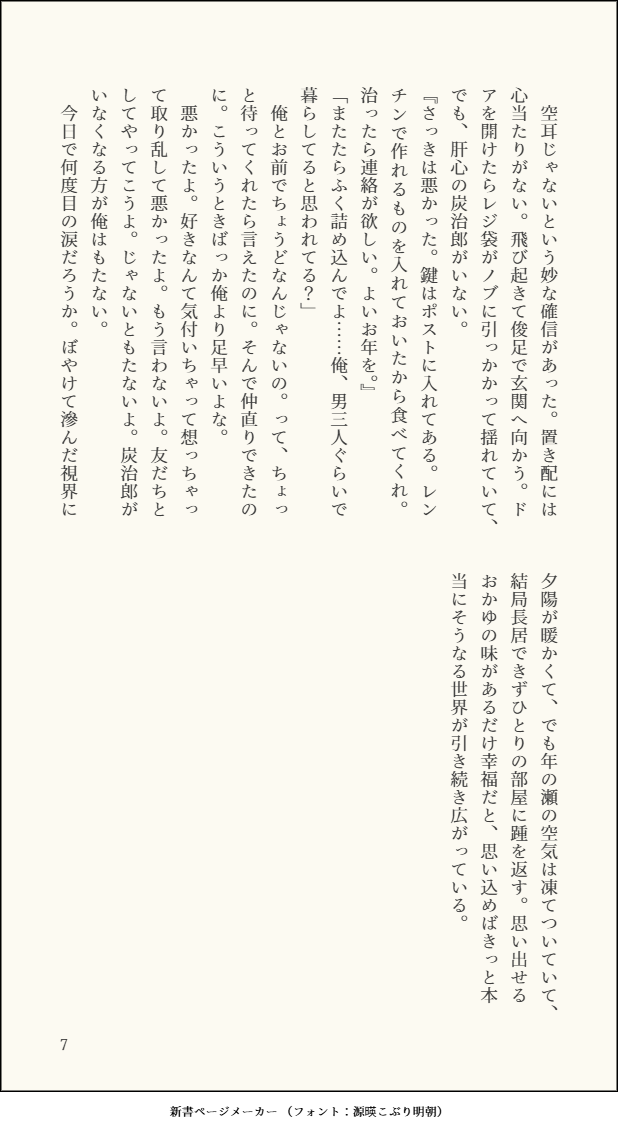
ないない
02
指がゆらりゆらりと踊るように舞って勝手にいたずらをした、ということにした。
ぜえいつ、と甘く呼ぶその声をなんとなく。その正体が炭治郎の声をなぞっただけの電子音だとしても、今すぐ聴きたかった。ああ、悪いな。悪いよな。でも出なくたっていいんだ。もちろんそんなこと期待してやしない。彼がデートなんだと指を指していたのはたしかに今日の日付だった。相手の女の子とも事情が通じている俺は今日はあの子のおうちに炭治郎がいることを知っている。
俺の家に上がったときの炭治郎の姿を思い出しながら、どうしようもなくなって、後戻りのきかないボタンを押している。名前を呼んでもらうだけで良かった。煙たく思ってもらって良かった。
切られるかなあ。ニコール。三コール。音切ってんのかな。そりゃそうか。なんで思い至らなかったんだろう。六コール。七コール。もう切ろ。八コール。九コール。
『もしもし?』
切るために耳から離した端末から俺に問いかける声が聞こえる。
『善逸か? もしもし?』
「お前、なんで出んの……」
『今日は予定があるって言っただろう。急ぎか? そうじゃないなら普通にメッセージで』
「馬鹿炭治郎」
『いくらなんでも脈絡がないぞ、なんなんだ』
好きだ
と言ってしまうなら今かなと思い巡らせながら、通話を切ってしまうこともできないまま、途方に暮れる。
「俺のうち、来て」
『だから今日は』
「知ってる。いいよ、何時になってもいいし泊めるから来て。炭治郎に会いたいから来て」
『今言えない話なのか?』
「話したい、じゃないって。会いたいの」
『善逸、だから』
「声聴きたかっただけって。じゃあな」
情けね~~~~~~~~~~~~と声が漏れて目を手のひらで覆って冷やす。これから冬がやってくるのが憂鬱だ。たかだか木枯らしが吹いたくらいでこのざまで、とても越冬できるとは思えない。
炭治郎がいないとできる気がしないんだよ、なあ、頼むよ。
✧
さっきはごめんな
別に来なくていいよ
邪魔して悪かった
返信不要の意思を伝えるスタンプで途切れているトーク画面に返信は結局しないまま、炭治郎は善逸のアパートの一室の手前まで来てしまって、そこまで来て引き返すわけもない。お開きにしてしまった逢瀬も、今更引き返したところで時間まで巻き戻ることはないのだ。いつも使っていたポストに突っ込まれていた合鍵もそのままだった。もし解消されていたら、炭治郎だって素直に帰れたのに。
鍵を開ける。玄関をくぐる。すでに日の暮れた部屋はどこの電気も点されていない。不在だろうか。たしかに静まりかえっている。しかしいつも使っていたスニーカーが玄関でたたずんでいる。確信のようなものを握りしめて炭治郎は部屋に上がった。「善逸、来たぞ」と申し訳程度の宣言を携えて。
洗面所。いない。リビング。いない。キッチンももちろんいない。寝室。ベッドの上。こんもりと盛り上がっている。自分が扉を開けた音に気付いていないわけがないはずなのに、微動だにしないその塊に不安が募る。もしかして体調でも悪かったのだろうか。自分に求められていたのは助けだったんだろうか。
「善逸? 寝てるのか? 具合が悪いのか?」
塊はなおも動かない。この状況で起こすのはより悪いかもしれない。悪いと思いながら、そのふくらみに手を乗せる。滑らせた。ときだった。
「なああああああああああんで、来ちゃうかなああああ、お前はさあ…………」
「起きてたのか」
「ほかの女とデート中の好きな子情けなく呼び出してずっとずっと膝抱えて待ってたのに寝こけて見逃すなんて真似するわけないだろうが、この俺だよ?」
「……」
「どうしたの哀れみに来た? 全然嬉しいんだけどね俺はそれでも。炭治郎ってそういう子だよね知ってる。そういうとこ嫌いになれなかったなあ最後まで」
「言ってる意味が、あまりよくわからないのだが」
「うんわかんなくていいよもちろん」
ベッドの縁にしゃがみこんで、そしたら背中を向けていた善逸がようやく寝返りを打って炭治郎と目を合わせる。金の髪が闇の中なのにふわふわきらめいている。懐かしいのは実際何度もまぐわったからだ。こういう場所で、善逸とふたりで。五感の方がよくおぼえている。
「炭治郎。なんで来ちゃうの。女の子になんて言ってきたの。うまくいったからその報告?」
「謝って帰ってもらった。……善逸が来い、と言うから」
「馬鹿炭治郎……大馬鹿……そのまま一生婚期逃せばいいよ」
「なんてこと言うんだ。用がないなら帰る」
「そうしてそのまま俺にうつつを抜かして一生隙を突かれてればいいよ、ねえ。俺一生炭治郎のこと好きだしおあいこじゃんねえ」
「さっきから、どさくさに紛れて告白されてるのは、俺の聞き間違いか……?」
だって恨み言を吐くような表情とその口から吐き出される文言が全く一致しない。尋ねて、ふと気付いたら手を握られていた。なんだと尋ねる余裕もない。心の底から震えて怯える匂いに圧倒されてしまう。ーー相手が善逸だから、余計になのだ。
「炭治郎、まだ俺のこと好き?」
「っ」
「ねえ炭治郎。目え逸らさないでよ。心臓の音が早い意味はなに? 炭治郎の口から教えて」
「……」
「匂いでわかんでしょ? お前にあてられてんだよ。好き。大好き。遅くなってごめんな。臆病でごめんな。ずっとそうだったし、今もそうだし、これからもそうだよ、お前以外にこんな気持ちになることないんだよ。どうにかしてくれよ。ほかの女の子ほっぽって俺のところに来てなんてめんどくさい頼み事、できるのも炭治郎だけだし聞いてくれるのも炭治郎だけだよ。ねえ好きっていって。俺のことまだ好きって言ってくれよ。またキスさせて、気失うまで抱かせて。いっぱい愛してるって言わせて」
「ばっ、もういい、もういい……っ」
「ごめんな炭治郎、ごめん。もう離さないからそうやってお前が信じられるまで俺のこと好きにしていいから。なんでもするからここにいてお願い。一生のお願い」
くるし、善逸、と、なんとか声を漏らして、肺がちぎれそうな抱擁からは解放されて、あとはとめどなく涙をこぼし続ける男の面が目の前に迫る。
「おれ、いや。炭治郎がほかのひとにとられるとかほんきでいやそうならないためだったらしんでもいいほんとうだから、炭治郎、炭治郎……」
「わかったからもう泣くなって」
「ほんと? ねえほんと? マジ? 俺のこと好き? 見捨てない?」
「……ああ、わかったから」
「うわあああああああああん」
鼻水も涙も一緒くたにして口づけをされる。もたれかかってくる身体を支えきれなくてふたりしとどに床で尻を打った。それでも飽き足らずに痛く痛く抱きしめられて、俺まで泣きたくなる。そんなに好きなら何であのとき離したりしたんだ。俺だって泣かなかったわけじゃないぞと責めると俺はその五倍は泣いてるとなぜかきっぱり宣言される。
「ごめんね炭治郎。一生こうやってふたりでいようよ」
「……遅い」
「うん。ごめんよ。もう間に合わない? 俺のこと嫌だって言う? でももう離せないんだよおごめんなあ」
いいよ全部もう許す俺も善逸が好きだ、とやっと問いに答える心地で告げると、たしかに俺の涙は善逸の涙に紛れてあっけなくどちらかの唇の中に溶けて馴染んでみわけがつかなくなった。
ないない
指がゆらりゆらりと踊るように舞って勝手にいたずらをした、ということにした。
ぜえいつ、と甘く呼ぶその声をなんとなく。その正体が炭治郎の声をなぞっただけの電子音だとしても、今すぐ聴きたかった。ああ、悪いな。悪いよな。でも出なくたっていいんだ。もちろんそんなこと期待してやしない。彼がデートなんだと指を指していたのはたしかに今日の日付だった。相手の女の子とも事情が通じている俺は今日はあの子のおうちに炭治郎がいることを知っている。
俺の家に上がったときの炭治郎の姿を思い出しながら、どうしようもなくなって、後戻りのきかないボタンを押している。名前を呼んでもらうだけで良かった。煙たく思ってもらって良かった。
切られるかなあ。ニコール。三コール。音切ってんのかな。そりゃそうか。なんで思い至らなかったんだろう。六コール。七コール。もう切ろ。八コール。九コール。
『もしもし?』
切るために耳から離した端末から俺に問いかける声が聞こえる。
『善逸か? もしもし?』
「お前、なんで出んの……」
『今日は予定があるって言っただろう。急ぎか? そうじゃないなら普通にメッセージで』
「馬鹿炭治郎」
『いくらなんでも脈絡がないぞ、なんなんだ』
好きだ
と言ってしまうなら今かなと思い巡らせながら、通話を切ってしまうこともできないまま、途方に暮れる。
「俺のうち、来て」
『だから今日は』
「知ってる。いいよ、何時になってもいいし泊めるから来て。炭治郎に会いたいから来て」
『今言えない話なのか?』
「話したい、じゃないって。会いたいの」
『善逸、だから』
「声聴きたかっただけって。じゃあな」
情けね~~~~~~~~~~~~と声が漏れて目を手のひらで覆って冷やす。これから冬がやってくるのが憂鬱だ。たかだか木枯らしが吹いたくらいでこのざまで、とても越冬できるとは思えない。
炭治郎がいないとできる気がしないんだよ、なあ、頼むよ。
✧
さっきはごめんな
別に来なくていいよ
邪魔して悪かった
返信不要の意思を伝えるスタンプで途切れているトーク画面に返信は結局しないまま、炭治郎は善逸のアパートの一室の手前まで来てしまって、そこまで来て引き返すわけもない。お開きにしてしまった逢瀬も、今更引き返したところで時間まで巻き戻ることはないのだ。いつも使っていたポストに突っ込まれていた合鍵もそのままだった。もし解消されていたら、炭治郎だって素直に帰れたのに。
鍵を開ける。玄関をくぐる。すでに日の暮れた部屋はどこの電気も点されていない。不在だろうか。たしかに静まりかえっている。しかしいつも使っていたスニーカーが玄関でたたずんでいる。確信のようなものを握りしめて炭治郎は部屋に上がった。「善逸、来たぞ」と申し訳程度の宣言を携えて。
洗面所。いない。リビング。いない。キッチンももちろんいない。寝室。ベッドの上。こんもりと盛り上がっている。自分が扉を開けた音に気付いていないわけがないはずなのに、微動だにしないその塊に不安が募る。もしかして体調でも悪かったのだろうか。自分に求められていたのは助けだったんだろうか。
「善逸? 寝てるのか? 具合が悪いのか?」
塊はなおも動かない。この状況で起こすのはより悪いかもしれない。悪いと思いながら、そのふくらみに手を乗せる。滑らせた。ときだった。
「なああああああああああんで、来ちゃうかなああああ、お前はさあ…………」
「起きてたのか」
「ほかの女とデート中の好きな子情けなく呼び出してずっとずっと膝抱えて待ってたのに寝こけて見逃すなんて真似するわけないだろうが、この俺だよ?」
「……」
「どうしたの哀れみに来た? 全然嬉しいんだけどね俺はそれでも。炭治郎ってそういう子だよね知ってる。そういうとこ嫌いになれなかったなあ最後まで」
「言ってる意味が、あまりよくわからないのだが」
「うんわかんなくていいよもちろん」
ベッドの縁にしゃがみこんで、そしたら背中を向けていた善逸がようやく寝返りを打って炭治郎と目を合わせる。金の髪が闇の中なのにふわふわきらめいている。懐かしいのは実際何度もまぐわったからだ。こういう場所で、善逸とふたりで。五感の方がよくおぼえている。
「炭治郎。なんで来ちゃうの。女の子になんて言ってきたの。うまくいったからその報告?」
「謝って帰ってもらった。……善逸が来い、と言うから」
「馬鹿炭治郎……大馬鹿……そのまま一生婚期逃せばいいよ」
「なんてこと言うんだ。用がないなら帰る」
「そうしてそのまま俺にうつつを抜かして一生隙を突かれてればいいよ、ねえ。俺一生炭治郎のこと好きだしおあいこじゃんねえ」
「さっきから、どさくさに紛れて告白されてるのは、俺の聞き間違いか……?」
だって恨み言を吐くような表情とその口から吐き出される文言が全く一致しない。尋ねて、ふと気付いたら手を握られていた。なんだと尋ねる余裕もない。心の底から震えて怯える匂いに圧倒されてしまう。ーー相手が善逸だから、余計になのだ。
「炭治郎、まだ俺のこと好き?」
「っ」
「ねえ炭治郎。目え逸らさないでよ。心臓の音が早い意味はなに? 炭治郎の口から教えて」
「……」
「匂いでわかんでしょ? お前にあてられてんだよ。好き。大好き。遅くなってごめんな。臆病でごめんな。ずっとそうだったし、今もそうだし、これからもそうだよ、お前以外にこんな気持ちになることないんだよ。どうにかしてくれよ。ほかの女の子ほっぽって俺のところに来てなんてめんどくさい頼み事、できるのも炭治郎だけだし聞いてくれるのも炭治郎だけだよ。ねえ好きっていって。俺のことまだ好きって言ってくれよ。またキスさせて、気失うまで抱かせて。いっぱい愛してるって言わせて」
「ばっ、もういい、もういい……っ」
「ごめんな炭治郎、ごめん。もう離さないからそうやってお前が信じられるまで俺のこと好きにしていいから。なんでもするからここにいてお願い。一生のお願い」
くるし、善逸、と、なんとか声を漏らして、肺がちぎれそうな抱擁からは解放されて、あとはとめどなく涙をこぼし続ける男の面が目の前に迫る。
「おれ、いや。炭治郎がほかのひとにとられるとかほんきでいやそうならないためだったらしんでもいいほんとうだから、炭治郎、炭治郎……」
「わかったからもう泣くなって」
「ほんと? ねえほんと? マジ? 俺のこと好き? 見捨てない?」
「……ああ、わかったから」
「うわあああああああああん」
鼻水も涙も一緒くたにして口づけをされる。もたれかかってくる身体を支えきれなくてふたりしとどに床で尻を打った。それでも飽き足らずに痛く痛く抱きしめられて、俺まで泣きたくなる。そんなに好きなら何であのとき離したりしたんだ。俺だって泣かなかったわけじゃないぞと責めると俺はその五倍は泣いてるとなぜかきっぱり宣言される。
「ごめんね炭治郎。一生こうやってふたりでいようよ」
「……遅い」
「うん。ごめんよ。もう間に合わない? 俺のこと嫌だって言う? でももう離せないんだよおごめんなあ」
いいよ全部もう許す俺も善逸が好きだ、とやっと問いに答える心地で告げると、たしかに俺の涙は善逸の涙に紛れてあっけなくどちらかの唇の中に溶けて馴染んでみわけがつかなくなった。
ないない
01
我妻善逸が竈門炭治郎の住むアパートの一室に文字通り転がり込むようになってからはじめて週をまたいだ。
土日はちゃんと家に帰るし二週間で案件の目処はつくはずだから本気で嫌になったら追い出していいからとまくしたてながら結局炭治郎の優しさにずぶずぶ甘えて休日出勤をこなしたあとも同じ部屋に帰って泥のように眠りこけていたら日曜は暮れていた。お互いにアラサーを迎えたいい大人とはいえまだまだ付き合いたてのまだまだいくらでも一緒にいたい頃合いである。主に善逸にとってである。会社に向かうには炭治郎の家が近くその上定期圏内だなんて神様があつらえたかのような口実だ。もちろん善逸にとってである。
帰宅時間の関係上ご飯は一方的に作ってもらう形になってしまっている。繁忙期だから転がり込んでいるという訳なので気にするなと炭治郎はからりと笑ってくれる。「俺はいつも定時で帰れているからな」と善逸を気遣う炭治郎はしかし自分よりも朝が早い。出勤前にできる部分をなるべくきれいに掃除するのはしかしあまり役には立っていないんだろうとは思いつつも気持ちを込めてこなしている。ときめき出埋め尽くされた同棲ごっこは、しかし負担が炭治郎の方に傾きながら、それを気にはしながらも、それでも目一杯に善逸は幸福を享受している。
「あああつっかれたあ……」
そして八日目の月曜日。本日の帰着地点も無事に視界に入って一気に気が抜けた。肩腰首を順番にごりごりごりごり回すと心がほうとぬくくなる。遅くなると伝えてたから炭治郎は驚くかな。今日の夕飯は何だろう。もうとっくに身体に馴染んでしまったような気もする黒い扉。金のドアノブと鍵穴。ポケットの中で握りしめる合鍵の感触に思わず笑い声を漏らしてしまいながらそうっと、宝箱を開けるみたいな手つきで鍵を開けて善逸はそのドアをくぐる。
こっそり近づいてうしろから抱きしめて脅かしてやろうか、喜ぶかなあ炭治郎は。それとも料理中は危ないと頬を膨らませてごまかすかなあ。ああはやく会いたいな、抱きしめたいな。くん、と鼻をきかせるとデミグラスソースらしい匂いが漂ってくる。ハンバーグだろうか。超超超楽しみ。善逸は口笛を吹きながらキッチンに急ぐ。
「あり、いねえ……」
電気はついているもののそこはもぬけの空だ。ああトイレにでも行ってんのかと思い直した。せっかくおどかそうとしたのになあと踵を返して洗面所に戻る。その途中にトイレがあって、どこか聞き覚えのあるーーもっと言えば男なら誰でも馴染みのある水音が耳を掠る。掠ってしまう。そして反射で足音を忍ばせて息を殺す。その木の板に耳を、そばたててしまう。
「っ、う……ぁ」
「……!!」
声が出そうになる口を手のひら必死に押さえる。ありふれたアパートの一室でトイレにだけ特殊防音が搭載されているはずもなく、もちろんもとより耳のいい善逸がこんなに聞き耳を立てれば中の音なんて筒抜けで──いや、駄目だろさすがに毎日毎日泊めてもらっている身でこんな超プライベートゾーン……でも聴く以外の選択肢ありますかね!? ねえ!?
「あ、っでるッ」
かあああああわい……………………。
今すぐ力任せに鍵を壊して扉をこじ開けて抱きしめたい。口づけたい。思う存分堪能して、それからその先、そのもっと先にも進みたい、ぜんぶぜんぶ炭治郎と、したい。
水を流す音が善逸を正気に戻す。俊足で洗面所に逃げた。疲労でそれどころではなく抜くのをサボっていたせいですっかりご立派になった下半身はあとで処理することとする。それよりも今後最低三ヶ月は貴重なオカズになるであろうかすかな喘ぎ声を何回も何回も何回もリピートして脳の隅の隅に厳重に保存する。ああでもすでにもう一度聴きたくなってしまっている。
なんとなく炭治郎に遠慮して二人は未だまぐわったことはなかった。交際を了承されてからひと月が経とうかという頃合いだし善逸も繁忙期に入ってしまったゆえ、遅すぎるということはないだろうが、善逸のほうはかなり長いこと──我慢の体感としてはすでに砂漠を歩く旅人と化している──こらえている方である。その我慢の質量を炭治郎は匂いで察していることも彼の鼓動の音から察しているが、なんにせよデリケートな話題ゆえ、ゆっくり話す機会がなければコミュニケーションは難しい。力任せに押し倒そうとすれば張り手が飛んでくること請け合いである。詳しくは言わないがもちろん実証済みである。
と、いうのに。
とんでもない爆弾だこれは。食事も睡眠もつかの間の休日のおかげでやや回復されていたおかげで一線を越えずにすんだが、殺人的な生活を強いられていた先週の半ばであれば間違いなくドアから出てきた炭治郎を襲っていただろう。ナイス月曜日。ナイス俺の理性。
ああそれにしてもどう持ちかけたら炭治郎は抱かせてくれるだろうか。──あの声を。一瞬で耳から善逸の体内に潜り込んで心臓を抱きしめたあの音を、どうしたらもう一度聞けるだろうか。もっともっと気が済むまで、炭治郎から絞り出せるだろうか。
「善逸! 帰ってたのか?」
「ッウワッ!!!!!!! マジですみませんでした!!!!!!!」
リピートしすぎてこっちに向かう炭治郎の足音さえ聞き逃す始末だ。洗面台に押しつけて下半身をなんとか彼の視界から隠して何食わぬ顔で手をぬらしハンドソープを手に取る。
「え、何の謝罪だ?」
「いや、ごめん……あんまり美味そうで、キッチンのハンバーグのソースちょっと舐めた」
「あれはパスタに絡めるソースだが、ハンバーグが埋まってるように見えたか?」
もう11月だというのに背中に流れ伝う汗をはっきりと味わいながらしゃかしゃかしゃかしゃかと手をこすり続ける。手もきれいになるわ下半身もすっかり萎えてくれるわで一石二鳥だ。
「でも、多く作ったから明日はハンバーグにするか。ありがとう、善逸」
「超楽しみ。はあ炭治郎今日もマジで疲れたよおねえ抱きしめていい?」
「はは、いいぞ。おいで」
あったかい心音だ。血の流れもまろやかで。善逸に抱きしめられて安心してるのかすうと息をするたびに炭治郎の力が抜けていく。背中をなで下ろされて、それはまったく性的な感触を伴っているわけではなかったのに。
それでもいま聴きたくてたまらないのは、この男の乱れた呼吸と、騒ぐ血流と、暴れる心音だった。「はああ……」
「善逸? もういいか? 腹も減っただろ。遅くなると聞いてたから、一緒に食べられて嬉しいよ」
「ねえ炭治郎……」
最初の時はあんなに真っ赤になっていたくせに、口づけにはすでにすっかり慣れて軽く受け流しさえする炭治郎がたまらない。そう遠くない未来に、平気で身体を交えるようになってしまってそれが日常になったなら。付き合いの長い恋人もいたことがあるから他人とそうなることは初めてではないのに、善逸は初恋を前にした中学生のごとく脳内をすんなり妄想に乗っ取られる。
「なんだ、善逸」
「好き」
「……俺も、だ」
瞳には器用に色欲が混ざっているというのに、本人の自認は純潔清廉なのだからたまらない。
いくら妄想に色めき立っていたって、当然お互いに中学生ではないわけだから、もっと満ち足りる方法を少なくとも善逸は知っているわけだから、足りない、となってしまう。それが惜しい。しかし、はやくもっとふかく、炭治郎にさわってみたい。
「じゃあ、おやすみ、善逸」
今は善逸の方が忙しい時期だからと客用布団を敷いてベッドを譲ろうとした炭治郎に、転がり込んでる身にお願いだからそんな鬼畜みたいなことさせないでおくれと頼み込んで、セミダブルにふたりの身体を押し込めて眠っていた。一日の終わりに用意された幸福そのものに包まれる時間だ。言うまでもなくひとりでベッドを使わせていただくより安眠効果が高い。
「なあ」
「ん?」
「炭治郎に聞きたいことあったんだけど聞いていい?」
「かしこまった話か?」
「いんや、全然」
仰向け同士になっていた身体をこてんと隣に転がして肩に腕を回す。抱きつく。太ももを彼の足に絡ませる。抱き枕にしているような格好だ。好きだなあ、幸せ者だなあ。
「ずいぶん甘えん坊だな」
「ん。そーなの疲れてるの甘やかして。ね、炭治郎」
「うん」
「俺はいつも抜くとき炭治郎で抜くんだけど炭治郎は誰で、何で、どんな風に抜くの?」
せっかく抱きしめ返そうとしてくれた身体がこわばる。もう男同士じゃんそんな構えなさんなともどかしくなりながらそこが好きだ。広げられかけてそこで止まってしまった炭治郎の胸に遠慮なく抱きつく。腕が勝手に善逸を包んでいる。
「抜く、って」
「自慰。オナニー。ひとりあそび」
「馬っ、鹿……」
「しないわけないよね男の子だもんね。ね、おしゃべりぐらいいいじゃんか付き合ってよ。ビンタはもう嫌だよ俺」
「……はあ」
きゅうと抱きしめられてむずと背筋が震える。闇で色が見えずとも体温で十分にわかる。真っ赤っかの頬をそれでも本能的に隠そうとしているのか、今度は炭治郎が善逸の胸にうずまろうとしている。何この子可愛すぎでしょうが女の子と付き合ったこともあるって言ってたのに何? 本当に何?
「善逸は、俺で」
「そ。も~お前に惚れてから、毎回、そう。炭治郎はどんな声で鳴くのかなあどんな反応すんのかなあどんな風に、イくのかなあ」
耳元でひくくささやく。隠れよう隠れようとするその頬に手を添える。上を向かせて、口づける。
「って、勝手に妄想しながら俺もイくの」
「……それを聞いて、俺にどうしろ、と」
「別に今はどうもしねえよ。いつか聞かせてねってだけ」
微笑んで、じいと見つめる。瞳を闇に慣らせば慣らすだけ、水の張った彼の瞳もよく見えるようになる。
「炭治郎。炭治郎はどう。聞かせて、聞きたい。こんなの俺だけなんて切ないなってなったんだよう。忙しいから心が弱っちゃってんの」
「……もう、ほんと」
「うん」
「朝になったら忘れろよ」
「もちろんだよそういうもんだよ。ほら、聞かせておくれ」
「……善逸、で、抜く。俺も」
うん、そっか。知ってる。って言いたかったけどやっぱ直に聞くとヤバいな。
だってお前俺のこと考えながらあんな声出すの。その声につながるのって俺の名前なの。それ本当? 本当だって教えておくれよ。聞かせて、聞かせて。
「ん。どんな俺がいるの。お前の頭の中にはさ」
「格好良い善逸だよ。こうやって、今俺の目の前にいる、善逸」
「へへ。そっか。俺もだよ。かわいい、炭治郎。そっか……」
ああとぶっきらぼうに返事してもう寝ると善逸の胸にうずまってしまう。でもさあ触れてるでしょ。お前のそうだね、その腹のあたりに、かたくて、あつい、それが。
「なんで」
「そりゃ、男ですもん。そのうちおさまるから」
「ああそう……」
気まずそうにもごもご唇を動かしたあと、しかし放置すると腹をくくったのか炭治郎は無理矢理目を閉じて深い呼吸を繰り返してみたりしている。自然な寝息とはほど遠く、きっと目が冴えていってしまう。
「俺はさあいつも風呂で抜くんだよ。まあ別に聞き耳立てられてても困ることなんて何もないんだけど。トイレで抜くなんて脇の甘いことしちゃってるときに限って早く帰ってきちゃって、ごめんな」
炭治郎が寝息を決め込むなら決め込めば良い。好きで好きでおかしくなってた。問い詰められれば善逸はそう抜かすつもりで、自分も目を閉じた。鼓動はいまだ暴れているが疲労が濃いのもまた事実だ。そのうちにおさまって眠れるだろう。我妻善逸様の理性は鉄壁なのである。
「……しってた」
前言撤回の瞬間である。
「え」
「……」
「え、待って今なんてえっちょっ炭治郎さん待って」
腕の中から炭治郎が逃げて背中を向けられる。セミダブルの端の端。逃げられれば逃げられるし、捕まえようとすればすぐ捕まる。ふたたび抱きしめる。
「善逸がいるの、知ってた!」
ベッドの上でなければ卒倒である。知ってたって? 知ってたってどういうことだ。知ってたってことか? え?
その上で? あの声を?
「いちばん近くに来て、聴かれてるのもわかってたけど、匂いが濃くて、とめられなかった、から……」
「えええちょっと待って本当に嘘でしょまさかの襲うルートが正解だった?」
「正解じゃない。間違いなく張り飛ばしてた」
「それもそれでなんでえええ……」
「善逸。俺はもう寝る」
「待って待って待って。断固延長希望。ていうか、あの、もう俺さあ、結構限界」
「ちょ、寝る。寝るってば」
さっきよりもっと張り詰めたものが腰に勝手にすり寄る。本能を膨らませたのはこの男だ。責任を取ってほしいだなんて女々しいことは言わない。謹んで面倒を見てほしい。
だって、それに、炭治郎だって、勃ってる。
「炭治郎。もっかい聴かせて。ねえ一回も二回ももう変わんないから。俺ねもう頭に刻みつけたから。それ聴きながらいまここで抜いたって別に良いんだけど、でも炭治郎もきもちくなろ。オカズのあげあいしよ」
「馬鹿善逸、馬鹿……」
「好き炭治郎。大好き。ね、いい? だめ? いい? いいよね? ごめんねちょーっとまだセックスはお預けだけどさ、ねえ、だからもっと楽しみになるようにえっちなことしよ」
いいよの言い方もわからないのだ。恥ずかしくて縮まるばかりのこの身体は。そんな三音肌から聞けば善逸には十分だった。──モノ同士がふれあうように、腰を寄せる。一緒くたに握りこむ。炭治郎が声を漏らす。
「わかんないとか気にしなくていいに決まってんでしょうよ。俺に任せてよ」
「ぜ、いつ……ぁ」
「うん。俺の触り方教えてあげるから。覚えて、使って」
「ばか……ッ」
「俺も覚えて、んで、……ごめんね、いっぱい使う」
スラックスも下ろさないままほとんど同時に一回目を迎える。週末には抱けるだろうか、と巡らせながら、月曜日を心底恨みながら、興奮の収まらない指で彼の下着のゴムに指をかけた。
ないない
我妻善逸が竈門炭治郎の住むアパートの一室に文字通り転がり込むようになってからはじめて週をまたいだ。
土日はちゃんと家に帰るし二週間で案件の目処はつくはずだから本気で嫌になったら追い出していいからとまくしたてながら結局炭治郎の優しさにずぶずぶ甘えて休日出勤をこなしたあとも同じ部屋に帰って泥のように眠りこけていたら日曜は暮れていた。お互いにアラサーを迎えたいい大人とはいえまだまだ付き合いたてのまだまだいくらでも一緒にいたい頃合いである。主に善逸にとってである。会社に向かうには炭治郎の家が近くその上定期圏内だなんて神様があつらえたかのような口実だ。もちろん善逸にとってである。
帰宅時間の関係上ご飯は一方的に作ってもらう形になってしまっている。繁忙期だから転がり込んでいるという訳なので気にするなと炭治郎はからりと笑ってくれる。「俺はいつも定時で帰れているからな」と善逸を気遣う炭治郎はしかし自分よりも朝が早い。出勤前にできる部分をなるべくきれいに掃除するのはしかしあまり役には立っていないんだろうとは思いつつも気持ちを込めてこなしている。ときめき出埋め尽くされた同棲ごっこは、しかし負担が炭治郎の方に傾きながら、それを気にはしながらも、それでも目一杯に善逸は幸福を享受している。
「あああつっかれたあ……」
そして八日目の月曜日。本日の帰着地点も無事に視界に入って一気に気が抜けた。肩腰首を順番にごりごりごりごり回すと心がほうとぬくくなる。遅くなると伝えてたから炭治郎は驚くかな。今日の夕飯は何だろう。もうとっくに身体に馴染んでしまったような気もする黒い扉。金のドアノブと鍵穴。ポケットの中で握りしめる合鍵の感触に思わず笑い声を漏らしてしまいながらそうっと、宝箱を開けるみたいな手つきで鍵を開けて善逸はそのドアをくぐる。
こっそり近づいてうしろから抱きしめて脅かしてやろうか、喜ぶかなあ炭治郎は。それとも料理中は危ないと頬を膨らませてごまかすかなあ。ああはやく会いたいな、抱きしめたいな。くん、と鼻をきかせるとデミグラスソースらしい匂いが漂ってくる。ハンバーグだろうか。超超超楽しみ。善逸は口笛を吹きながらキッチンに急ぐ。
「あり、いねえ……」
電気はついているもののそこはもぬけの空だ。ああトイレにでも行ってんのかと思い直した。せっかくおどかそうとしたのになあと踵を返して洗面所に戻る。その途中にトイレがあって、どこか聞き覚えのあるーーもっと言えば男なら誰でも馴染みのある水音が耳を掠る。掠ってしまう。そして反射で足音を忍ばせて息を殺す。その木の板に耳を、そばたててしまう。
「っ、う……ぁ」
「……!!」
声が出そうになる口を手のひら必死に押さえる。ありふれたアパートの一室でトイレにだけ特殊防音が搭載されているはずもなく、もちろんもとより耳のいい善逸がこんなに聞き耳を立てれば中の音なんて筒抜けで──いや、駄目だろさすがに毎日毎日泊めてもらっている身でこんな超プライベートゾーン……でも聴く以外の選択肢ありますかね!? ねえ!?
「あ、っでるッ」
かあああああわい……………………。
今すぐ力任せに鍵を壊して扉をこじ開けて抱きしめたい。口づけたい。思う存分堪能して、それからその先、そのもっと先にも進みたい、ぜんぶぜんぶ炭治郎と、したい。
水を流す音が善逸を正気に戻す。俊足で洗面所に逃げた。疲労でそれどころではなく抜くのをサボっていたせいですっかりご立派になった下半身はあとで処理することとする。それよりも今後最低三ヶ月は貴重なオカズになるであろうかすかな喘ぎ声を何回も何回も何回もリピートして脳の隅の隅に厳重に保存する。ああでもすでにもう一度聴きたくなってしまっている。
なんとなく炭治郎に遠慮して二人は未だまぐわったことはなかった。交際を了承されてからひと月が経とうかという頃合いだし善逸も繁忙期に入ってしまったゆえ、遅すぎるということはないだろうが、善逸のほうはかなり長いこと──我慢の体感としてはすでに砂漠を歩く旅人と化している──こらえている方である。その我慢の質量を炭治郎は匂いで察していることも彼の鼓動の音から察しているが、なんにせよデリケートな話題ゆえ、ゆっくり話す機会がなければコミュニケーションは難しい。力任せに押し倒そうとすれば張り手が飛んでくること請け合いである。詳しくは言わないがもちろん実証済みである。
と、いうのに。
とんでもない爆弾だこれは。食事も睡眠もつかの間の休日のおかげでやや回復されていたおかげで一線を越えずにすんだが、殺人的な生活を強いられていた先週の半ばであれば間違いなくドアから出てきた炭治郎を襲っていただろう。ナイス月曜日。ナイス俺の理性。
ああそれにしてもどう持ちかけたら炭治郎は抱かせてくれるだろうか。──あの声を。一瞬で耳から善逸の体内に潜り込んで心臓を抱きしめたあの音を、どうしたらもう一度聞けるだろうか。もっともっと気が済むまで、炭治郎から絞り出せるだろうか。
「善逸! 帰ってたのか?」
「ッウワッ!!!!!!! マジですみませんでした!!!!!!!」
リピートしすぎてこっちに向かう炭治郎の足音さえ聞き逃す始末だ。洗面台に押しつけて下半身をなんとか彼の視界から隠して何食わぬ顔で手をぬらしハンドソープを手に取る。
「え、何の謝罪だ?」
「いや、ごめん……あんまり美味そうで、キッチンのハンバーグのソースちょっと舐めた」
「あれはパスタに絡めるソースだが、ハンバーグが埋まってるように見えたか?」
もう11月だというのに背中に流れ伝う汗をはっきりと味わいながらしゃかしゃかしゃかしゃかと手をこすり続ける。手もきれいになるわ下半身もすっかり萎えてくれるわで一石二鳥だ。
「でも、多く作ったから明日はハンバーグにするか。ありがとう、善逸」
「超楽しみ。はあ炭治郎今日もマジで疲れたよおねえ抱きしめていい?」
「はは、いいぞ。おいで」
あったかい心音だ。血の流れもまろやかで。善逸に抱きしめられて安心してるのかすうと息をするたびに炭治郎の力が抜けていく。背中をなで下ろされて、それはまったく性的な感触を伴っているわけではなかったのに。
それでもいま聴きたくてたまらないのは、この男の乱れた呼吸と、騒ぐ血流と、暴れる心音だった。「はああ……」
「善逸? もういいか? 腹も減っただろ。遅くなると聞いてたから、一緒に食べられて嬉しいよ」
「ねえ炭治郎……」
最初の時はあんなに真っ赤になっていたくせに、口づけにはすでにすっかり慣れて軽く受け流しさえする炭治郎がたまらない。そう遠くない未来に、平気で身体を交えるようになってしまってそれが日常になったなら。付き合いの長い恋人もいたことがあるから他人とそうなることは初めてではないのに、善逸は初恋を前にした中学生のごとく脳内をすんなり妄想に乗っ取られる。
「なんだ、善逸」
「好き」
「……俺も、だ」
瞳には器用に色欲が混ざっているというのに、本人の自認は純潔清廉なのだからたまらない。
いくら妄想に色めき立っていたって、当然お互いに中学生ではないわけだから、もっと満ち足りる方法を少なくとも善逸は知っているわけだから、足りない、となってしまう。それが惜しい。しかし、はやくもっとふかく、炭治郎にさわってみたい。
「じゃあ、おやすみ、善逸」
今は善逸の方が忙しい時期だからと客用布団を敷いてベッドを譲ろうとした炭治郎に、転がり込んでる身にお願いだからそんな鬼畜みたいなことさせないでおくれと頼み込んで、セミダブルにふたりの身体を押し込めて眠っていた。一日の終わりに用意された幸福そのものに包まれる時間だ。言うまでもなくひとりでベッドを使わせていただくより安眠効果が高い。
「なあ」
「ん?」
「炭治郎に聞きたいことあったんだけど聞いていい?」
「かしこまった話か?」
「いんや、全然」
仰向け同士になっていた身体をこてんと隣に転がして肩に腕を回す。抱きつく。太ももを彼の足に絡ませる。抱き枕にしているような格好だ。好きだなあ、幸せ者だなあ。
「ずいぶん甘えん坊だな」
「ん。そーなの疲れてるの甘やかして。ね、炭治郎」
「うん」
「俺はいつも抜くとき炭治郎で抜くんだけど炭治郎は誰で、何で、どんな風に抜くの?」
せっかく抱きしめ返そうとしてくれた身体がこわばる。もう男同士じゃんそんな構えなさんなともどかしくなりながらそこが好きだ。広げられかけてそこで止まってしまった炭治郎の胸に遠慮なく抱きつく。腕が勝手に善逸を包んでいる。
「抜く、って」
「自慰。オナニー。ひとりあそび」
「馬っ、鹿……」
「しないわけないよね男の子だもんね。ね、おしゃべりぐらいいいじゃんか付き合ってよ。ビンタはもう嫌だよ俺」
「……はあ」
きゅうと抱きしめられてむずと背筋が震える。闇で色が見えずとも体温で十分にわかる。真っ赤っかの頬をそれでも本能的に隠そうとしているのか、今度は炭治郎が善逸の胸にうずまろうとしている。何この子可愛すぎでしょうが女の子と付き合ったこともあるって言ってたのに何? 本当に何?
「善逸は、俺で」
「そ。も~お前に惚れてから、毎回、そう。炭治郎はどんな声で鳴くのかなあどんな反応すんのかなあどんな風に、イくのかなあ」
耳元でひくくささやく。隠れよう隠れようとするその頬に手を添える。上を向かせて、口づける。
「って、勝手に妄想しながら俺もイくの」
「……それを聞いて、俺にどうしろ、と」
「別に今はどうもしねえよ。いつか聞かせてねってだけ」
微笑んで、じいと見つめる。瞳を闇に慣らせば慣らすだけ、水の張った彼の瞳もよく見えるようになる。
「炭治郎。炭治郎はどう。聞かせて、聞きたい。こんなの俺だけなんて切ないなってなったんだよう。忙しいから心が弱っちゃってんの」
「……もう、ほんと」
「うん」
「朝になったら忘れろよ」
「もちろんだよそういうもんだよ。ほら、聞かせておくれ」
「……善逸、で、抜く。俺も」
うん、そっか。知ってる。って言いたかったけどやっぱ直に聞くとヤバいな。
だってお前俺のこと考えながらあんな声出すの。その声につながるのって俺の名前なの。それ本当? 本当だって教えておくれよ。聞かせて、聞かせて。
「ん。どんな俺がいるの。お前の頭の中にはさ」
「格好良い善逸だよ。こうやって、今俺の目の前にいる、善逸」
「へへ。そっか。俺もだよ。かわいい、炭治郎。そっか……」
ああとぶっきらぼうに返事してもう寝ると善逸の胸にうずまってしまう。でもさあ触れてるでしょ。お前のそうだね、その腹のあたりに、かたくて、あつい、それが。
「なんで」
「そりゃ、男ですもん。そのうちおさまるから」
「ああそう……」
気まずそうにもごもご唇を動かしたあと、しかし放置すると腹をくくったのか炭治郎は無理矢理目を閉じて深い呼吸を繰り返してみたりしている。自然な寝息とはほど遠く、きっと目が冴えていってしまう。
「俺はさあいつも風呂で抜くんだよ。まあ別に聞き耳立てられてても困ることなんて何もないんだけど。トイレで抜くなんて脇の甘いことしちゃってるときに限って早く帰ってきちゃって、ごめんな」
炭治郎が寝息を決め込むなら決め込めば良い。好きで好きでおかしくなってた。問い詰められれば善逸はそう抜かすつもりで、自分も目を閉じた。鼓動はいまだ暴れているが疲労が濃いのもまた事実だ。そのうちにおさまって眠れるだろう。我妻善逸様の理性は鉄壁なのである。
「……しってた」
前言撤回の瞬間である。
「え」
「……」
「え、待って今なんてえっちょっ炭治郎さん待って」
腕の中から炭治郎が逃げて背中を向けられる。セミダブルの端の端。逃げられれば逃げられるし、捕まえようとすればすぐ捕まる。ふたたび抱きしめる。
「善逸がいるの、知ってた!」
ベッドの上でなければ卒倒である。知ってたって? 知ってたってどういうことだ。知ってたってことか? え?
その上で? あの声を?
「いちばん近くに来て、聴かれてるのもわかってたけど、匂いが濃くて、とめられなかった、から……」
「えええちょっと待って本当に嘘でしょまさかの襲うルートが正解だった?」
「正解じゃない。間違いなく張り飛ばしてた」
「それもそれでなんでえええ……」
「善逸。俺はもう寝る」
「待って待って待って。断固延長希望。ていうか、あの、もう俺さあ、結構限界」
「ちょ、寝る。寝るってば」
さっきよりもっと張り詰めたものが腰に勝手にすり寄る。本能を膨らませたのはこの男だ。責任を取ってほしいだなんて女々しいことは言わない。謹んで面倒を見てほしい。
だって、それに、炭治郎だって、勃ってる。
「炭治郎。もっかい聴かせて。ねえ一回も二回ももう変わんないから。俺ねもう頭に刻みつけたから。それ聴きながらいまここで抜いたって別に良いんだけど、でも炭治郎もきもちくなろ。オカズのあげあいしよ」
「馬鹿善逸、馬鹿……」
「好き炭治郎。大好き。ね、いい? だめ? いい? いいよね? ごめんねちょーっとまだセックスはお預けだけどさ、ねえ、だからもっと楽しみになるようにえっちなことしよ」
いいよの言い方もわからないのだ。恥ずかしくて縮まるばかりのこの身体は。そんな三音肌から聞けば善逸には十分だった。──モノ同士がふれあうように、腰を寄せる。一緒くたに握りこむ。炭治郎が声を漏らす。
「わかんないとか気にしなくていいに決まってんでしょうよ。俺に任せてよ」
「ぜ、いつ……ぁ」
「うん。俺の触り方教えてあげるから。覚えて、使って」
「ばか……ッ」
「俺も覚えて、んで、……ごめんね、いっぱい使う」
スラックスも下ろさないままほとんど同時に一回目を迎える。週末には抱けるだろうか、と巡らせながら、月曜日を心底恨みながら、興奮の収まらない指で彼の下着のゴムに指をかけた。
ないない
熱が下がったことを告げるメッセージとともに初詣の誘いが善逸から届いたのは彼の家を訪ねた翌日の夜のことだった。毛布に鼻を埋めてベッドの中で身を丸めながら、それなら自分の熱も明日には下がるだろうかと思いを馳せる。
『すぐ治って良かった!』
『だが、俺も熱を出して寝込んでいるところでな』
『来週なら日を合わせられると思う。初詣はそのあたりでいいか?』
充電コードにスマホをつないでそれきり背を向ける。おそらく当分は震えることのない携帯を気にしないようにして結局気にしてしまいながら、目を閉じては開いてを繰り返す。
しばらくそうしていてもうまく眠れないから何か腹に入れようかと起き上がったときだった。インターホンが静まりかえった部屋の空気を裂くように響く。通販でも頼んでいたかと思い返しながら出れば、
「炭治郎! 俺だよ~! 大丈夫か!?」
声を聞いて驚く。抑えきれず鼓動を跳ねさせながらその理由は驚いたからだということにしながら玄関のドアを開ければ金の髪が揺れている。看病しにきたんだぜ、と彼は俺に向かって得意げに微笑みかける。
そうして、手厚く想い人に面倒を焼いたのが返ってくるのは想像以上に嬉しいことを俺ははじめて知る。
新鮮な気づきはあっという間に胸を満たし、両手に提げられたぱんぱんの袋を目の当たりにしてごまかしようもなく気持ちが浮き足立っていた。
「いや、看病つったらおこがましいよな。俺が移したんだし。ごめんなあ。せっかくの年越しなのになあ」
昨日帰ってくれと告げられたのは怒らせたわけでも許されなかったわけでもなかった。安堵で頬が熱くなる。自分が発熱していたことを思い出し視界が霞んだ。善逸が心配そうに自分を見つめていて、笑顔を取り繕う。
「実家だと気を遣わせるから帰ってきたんだが、善逸が来てくれて助かった。ちょうどなにか食べようとしてたところで」
「わかるぜ。独りで寝込んでるときついよな」
「風邪なんて引くことなかったから、初めてなんだ。お前がいてくれるなら心強いよ」
「おまっ……それは、マジでごめん……」
「気にするな。俺も年の瀬で気が抜けていたんだろう」
しかし、やはり身体が弱っているときに会うのはいただけない。あの泣き顔は忘れてくれただろうか。確かめたくなったのを断ち切り、善逸を部屋に招く。
がちゃがちゃがしゃんとあまり馴染みのない調理音がキッチンからうっすら聞こえてくる。気にしつつ言われたとおりおとなしく寝たふりをしているのだが
「あちっ!! あっちょっぎゃぁああぁっ」
無視しきれない叫び声が飛んできてさすがに起き上がる。頭を抱えている善逸に大丈夫かと問いつつ背後からシンクをのぞき込めば、どろりとした白いおかゆとレトルトの袋が見事ぶちまけられていた。その隣で吹きこぼれそうになっていた湯の火を止める。散乱している材料を見るに、どうやら味噌汁も作ろうとしてくれていたらしい。
「ごめんよたんじろお……でも普段はこんなヘマしないのよ? ホラ、レンチンより湯煎の方が美味いのかなあとかさ……時間かかる方が手間暇かかってうまくなるとかそういう摂理あるじゃん? 料理って」
「あはは、味は変わらないんじゃないか? あまりこういうのを使ったことがないからわからないが……」
「いやいや待ってちゃんと片付けますから。手出ししないで! ほら寝てて!」
「さすがにほっとけないぞ」
勿体ないがとりあえずおかゆを捨てなくてはとふきんを引っ張り出す。銀色の上にぶちまけられた白色は容赦なく飛び散っている。ちょうど破裂しそうになっていた自分の恋心の顛末と重なり、いたたまれない気持ちでシンクを拭う。
──今更悲観するまでもなくこの恋は始まった瞬間から枯れていたはずだった。
唯一無二のこの親友が無類の女好きであることは付き合いの始まった小学生の頃から健在だったし、なんだかんだ恋人もいなくなってはまたできてを繰り返していたのだ。期待をかけられそうな現実は一年に数回、こんな風にひらひらと気まぐれに降り落ちてはまた去って行く。こちらから縁でも切らなければこれからも永遠にだ。
いつもは容易く我慢がきくのに今夜はなぜか難しい。難しい、ということにしてしまいたいのだろう。普段よりは弱った身体を理由にしたいのだろう。そんな向こう見ずな意志で行動を起こして、壊してしまったあとに後悔しないだろうか。俺にはわからない。──おかゆは手の中のふきんに拭い去られ、そのままポリ袋に捨てられる。手狭なキッチンで男ふたりが並べば、嫌でも肩と肩が触れてしまう。不用意に顔を赤くしないように深く呼吸をしながら淡々と片付ける。
「でもほら、本番じゃなくてよかっただろ」
「本番? って?」
「これから善逸も恋人の看病をするかもしれないし、その練習になるなら俺も嬉しいよ」
「ああ、そういうこと……っていやいやだから掃除は俺がやるって! 寝てなさいよお前は!」
「ふたりでやった方がはやい……」
「なんかフラフラじゃんね!? 大丈夫じゃないでしょ!? 薬飲む!? 熱が高いのか? 頭痛い?」
──ああ、どうにもいただけない。
炭治郎? と名を呼ぶ善逸の手のひらが額に触れて、そこから熱が生まれて爆ぜて、どうにも楽になりたくて。逃れようと後ろに引いた足下が頼りなくふらついて
「ちょっと、……」
「っ……善逸」
腰を抱きとめられてしまえばもう駄目だった。つややかな瞳を、最後に捉える。──ずっと本当は、溶かされてしまいたかった。
「好きだ、善逸」
「え、……」
「ずっと好きだった。でもずっと言うつもりもなかった」
ああ、こんなにも身体が軽くなるんだな。震える声で気持ちを吐き出せば心が鎮まって清々しい。不思議な感慨だった。──こんな気持ちさえ、これまで数多と貰ってきた、善逸が教えてくれたもののひとつとなる。
「忘れてくれてかまわない。このまま友だちでい続けてくれたら、俺は嬉しい」
善逸は優しいから、俺がしゃがみこめばつられて一緒に座り込んでくれる。縫い止められたように背中に乗った手が剥がれる瞬間をおそろしく思いながら、しかし結局はお前を抱きしめて拒まれる勇気を出せたことに胸が熱くなっている。
「お前ね」
「……なんだ?」
「俺も炭治郎と同じ気持ちかもって疑ったことはなかった?」
「え」
背中を撫で下ろされて、身体が震える。気持ちは一瞬で動転して、善逸の言葉を噛み砕いて理解しようとして、うまくいかない。それはあまりにも予想と外れた台詞だったから。
「どういう、意味だ」
「俺もお前が好きだよ。炭治郎」
「ちょ、ちょっと待ってくれ」
「ふふ。焦ってんの珍し。まあ、俺もちゃんと動揺してるから安心しなって」
「おい善逸。鼻血が」
「ふっふっふ……お前に惚れてるって自覚しただけで熱出すんだから鼻血くらい出るでしょうよ……」
「なんでそんなに得意げなんだ!」
なにひとつ現実を処理できないままとりあえずティッシュを掴んで鼻に当てて、その頃にはすっかり自身の頭痛はなりを潜めていたんだから現金なものだ──
***
作り直したおかゆをとりあえず食べさせてもらって、そのままソファで寝落ちていたらしい。年の瀬で慌ただしくて寝不足だったこともあるし、現実味のない現実を処理する時間が必要だったんだろう。隣で同じように俺にもたれて眠り込んでしまっている善逸を、おぼろながらにようやく受けとめつつある。
年越しを迎える夜のテレビなんて賑やかな番組で埋まっているはずなのに、流れていたのはやけに静かな雪景色だった。流した本人が寝こけているところから察するに、適当に選ばれた映画らしい。
「あー……寝てた」
「おはよう、善逸」
「ん。おはよ、炭治郎」
吐息のように囁いて俺をのぞき込む瞳が白い画面に照らされてどこか熱っぽい。夢じゃなかったんだな。こぼれたつぶやきはか細くて善逸はなにか苦いものでも飲み下すように唇を一瞬震わせる。
「欲を言うならもう一日我慢してほしかったけどね。病人が相手じゃ生殺しだわ……」
「はは。墓まで持っていくつもりだったんだ。あのとき言わなきゃ一生言わないままだったろうな」
「どっちにせよ俺から言ってたよ。炭治郎と違って我慢きかないの」
本音を言えばその辺りのことをもっと詳しく聞きたいが、どんな風に掘り下げれば良いのかうろたえているうちに「初詣どこいこうなあ」と話題がすり替わる。この男との距離を純粋に忘れる。砂時計の中で砂が落ちるようにこともなげに転がっていく会話の傍らで、べったりと自分に寄りかかる二の腕とくっつきそうに近い白い頬のせいで。
「もーう。そんなカオしないの!」
頬に受けたのは軽くて柔いくちづけだった。互いの動揺に蓋をするように善逸の熱い手のひらが目を塞ぐ。一拍おいて顔にどっと熱がたまる。すぐにふたつの温度は馴染んでどっちのものか見分けが付かなくなった。
映画はいつの間にかエンドロールを流し終え、番組に切り替わったテレビがいよいよ年越しのカウントダウンを刻み始める。
「来年も善逸とずっと仲良くやっていけますように」
「え?」
「今年の初詣の願いことだ」
「それ人に言っちゃ意味ないやつね」
「善逸の同意がいるだろう。お前は例外だよ」
「うぃひひ、たしかにね?」
安心しなさいよ絶対叶うから、と頭を撫でられているあいだにハッピーニューイヤーを告げた画面はにぎやかな祝福で埋め尽くされていた。
「あけましておめでと、たんじろ」
「ああ。おめでとう、善逸」
ありふれた挨拶さえ色が変わって自分の腹に落ちていく。相も変わらず夢のような現実がなだらかに始まって、夜が明ければきっとずっと広がっていく。
ないない
ないない